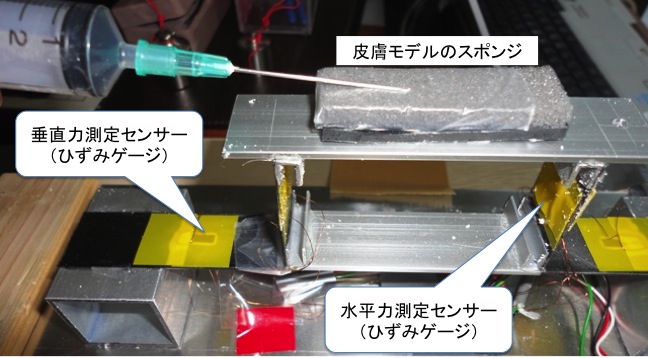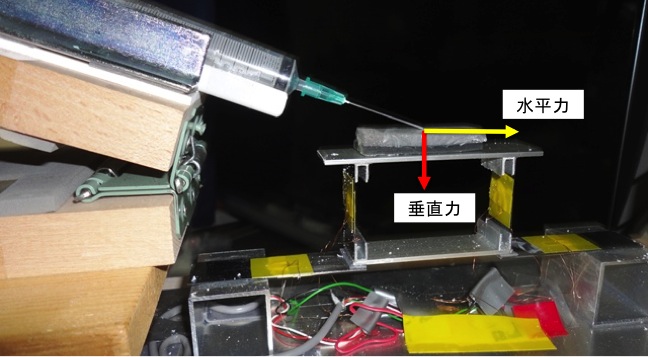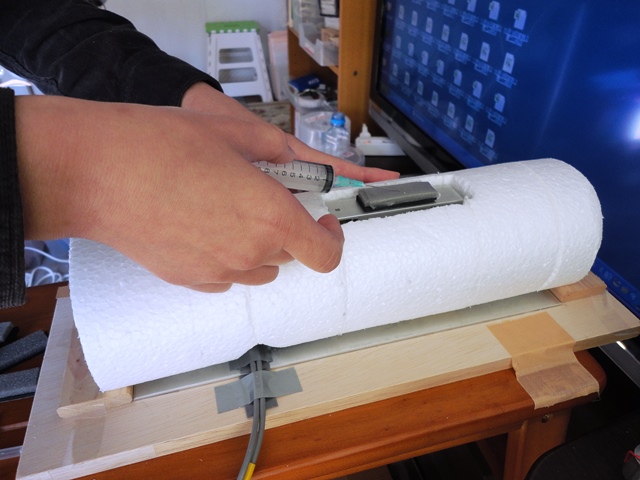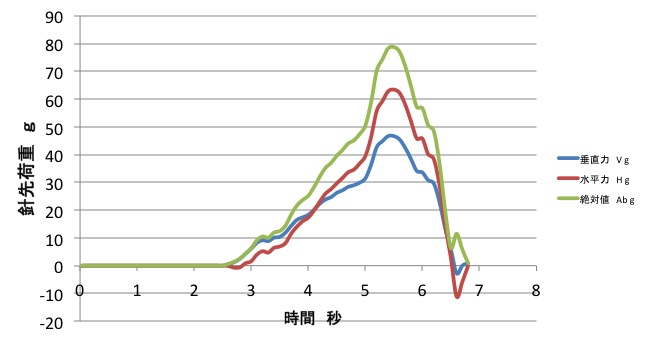�@�����i2014.1.18�j�͓y�j���B�K���ɂȂ��Ă��钩6��������̃��W�I�̑��E�X�g���b�`�E���Ɍ��ɎQ������B��6��20���Ƃ��o��B�ق�̏��������閾���̖��邳�͑������悤�ȋC�����邪�A�܂��A���ς�炸�Â��������B��������̂͂��A���ւɒ݂��Ă��鉷�x�v�̓}�i�X5�����w���Ă���B�h����́A�ȑO�ɔ�����悭�Ȃ菕���邪�A�w�悪�₽���B�����𗽂������̎�܂����ďo�����邪�w��͗₽���B���̂��߁A��܂�2�g����d�ɂ��Ă���B��N�̂悤�Ɍ��U�Ƀ��W�I�̑��E�X�g���b�`�E���Ɍ����s�����B���N���A�ł�����肱�̒��̉^���͑����A���N�ɋC���������Ǝv��������Ă���B
�@���H���ς܂��ƁA����ǂ̓m���f�B�b�N�E�E�H�[�L���O�iN.W.�j���҂��Ă���B������́A�L�������Ń|�[���������đ����A��҂ɕ����̂ŁA�^���������Ƃ����������킭�B����x�A��k�m���f�B�b�N�E�E�H�[�L���O�ɎQ�����Ă���B����ɉ�����N��ɓ��Ԏs�ɂ�N.W.�̃N���u�����邱�Ƃ�m�����ɂȂ�A�n���ł�N.W.���s����@��ł����B�n����N.W.�̖��̂́u���Ԏs�m���f�B�b�N�E�E�H�[�L���O�A���A���~���O��v�Ƃ����B���Ԏs����3�ق�N.W.����邻�������A���~���O��Ƃ���N.W.���D�̉����ɋ߂��Ƃ���ɂ��邱�Ƃ�m�����B���̉�̃��[�_�[�͐��`�O�ȊW�̐搶�ŁA�搶�̊��҂�������l���Q�����Ă���悤���B���҂���͕��s���x�𐧌������̂ŁA�����̌���҃O���[�v�Ƌ����̃O���[�v�ɕʂ�ĕ����B
�@������N.W.�͍ʂ̐X���Ԍ����B�����n�߂�O�ɁA�K�������̑����s���B���̎��_�ŁA���������̐�����ŏ���1�q�ł�����d�˂�ɂ�āA�R�q�A�S�q�����悤�ɂƎw��������B�����ΕK�����g�̌��N�ɂȂ���Ƃ������������������B1���Ԕ��قǕ�������ɂ̓N�[���_�E���̉^�����s���B���̉�ɂ܂�3���Q�����Ă��Ȃ����A�Q������Ɖ���J�[�h�Ƀn���R�������Ă��炦��B����͉Ẵ��W�I�̑��Ŏq�ǂ��B���J�[�h�ɏo�Ȉ�������Ă��炤�̂Ɠ����ł�B���̐��������Ă����Ɨ�݂ɂȂ邵�A�y���݂ɂ��Ȃ�B�J�[�h�Ƀn���R�������ς��ɂȂ�����A�Ȃɂ��v���[���g������Ƃ����N.W.���s���y���݂�������̂����I�IN.W.�̏o�ȉ́A���̃n���R�̐�������Β���������BN.W.�r���ŏI�����������B���̎��́A���l����w�����̕���N.W.���I����|��K���m�点�ċA�郋�[��������B
�@N.W.���I�������߂Ɉ�x����ɖ߂�A������A�f����ς邽�߂ɍĂы���ցB�f��̖��O�́u����Ȃ�A�A�h���t�v�B���̉f��́A�S���̉f���20�قł������f����Ă��Ȃ��悤�ŁA�����o������߂��̃��i�C�e�b�h�E�V�l�}���Ԃł͕��f���Ă��Ȃ��B���̂��߁A�킴�킴����̂ǐ^�ɂ���“�V�l�X�C�b�`���”�֍s�����B�����́A�������v�X���������S���ڌ����_����߂��A���傤�nj�ؖ{�^��̖{�X�̐^���ɂ���B�f��ق������ɂ����Ǝv�������A��ؖ{�^��X���Ƃ������ƂŁA�����ɂ킩�����B�ߌ�4��������̊J�n�ŁA�Z�������O�ɏI������B
�@���̉f��́A����E���ōr��ʂĂ��������c�f����Ԃ������܂�5�l�̌Z��o���̊�������ł���B���͈قȂ邪�A�푈����������ɓ��l�ȔߎS�Ȗڂɂ����A�q������𑗂����҂ɂƂ��ċ������o����B�����Ă����܂ŗ���ꂽ�̂��s�v�c�Ȃ��炢���B���e�͗c��2�l�̒�������A��A1945�N3��9���̖�A�̕�������邽�ߔG�炵���z�c�ɂ��Ԃ�A�T�˂�����c��̌��⋴�܂ʼn̕�������������Ƃ����B���͂Ƃ����ƁA�R�`���đ�s����쒬�̉���X�ɂ������������قɏW�c�a�J�����A��̋��낵����̌����Ă��Ȃ��B�I���A�R�`���瓌���֖߂����玩��͋�P�ŏĂ���ĂȂ������e�ƒ�2�l�͖��������͌����Ɉڂ��Ă����B���͒��ڐ�Ɍ������邱�Ƃ͂Ȃ��������A���e����ߎS�Șb��������Ă���̂ŁA�����ς��f��u����Ȃ�A�A�h���t�v�̎�l����Z��o���̋C�����͕�����B�����̉f��ł������B�y20141.23�z
�ʐ^1�F�ܑ����ꂽ�����₷���V��������������Makiko
�ʐ^2�F�������~�̒r�̔ȂŎb����x��
�ʐ^3�F�l�Ȃ��Ă���J���Ȃ̂��A�a�����˂��肵�Ă���̂�
�ʐ^4�F��͉f��u����Ȃ�A�A�h���t�v���V�l�X�C�b�`����Ŋӏ�
2014.1.23�@����ɂċL�� |