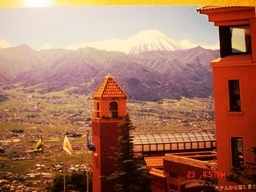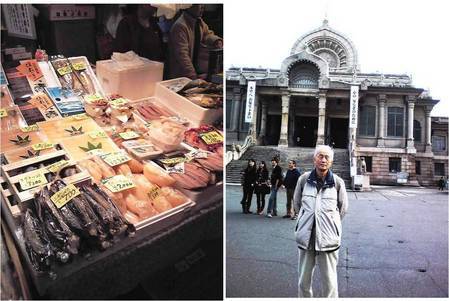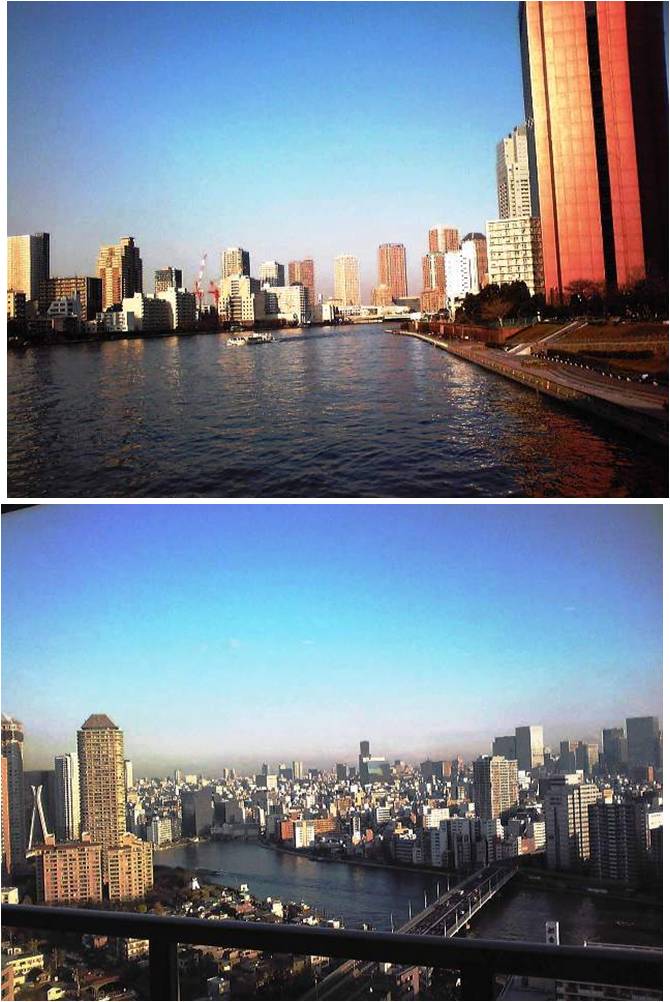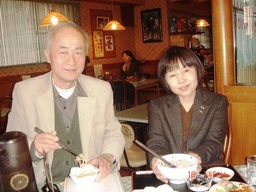| �@12��21���A�䂪�Ƃɒ~�M���g�[��i�������i�}�C�R�������j�j���������B�~�M�g�[��̐������́A�u�d�C�~�M�g�[�탆�j�f�[���i�^�ԁFVUEi50J�j�v�Ƃ����A���f�B���v���b�N�X�E�W���p�����p���H����A���������i�ł���B�戵���̓p�i�\�j�b�N�d�H�z�[���G���W�j�A�����O���ŁA�ݒu�H���͓����Z�L�X�C�t�@�~�G�X�����S�����Ă���B�ݒu�ꏊ��10��̋��Ԃł���B
�@�[��d�͂��g���Ė钆�ɉ����ɂ��A�����ɂ��̓����g���Ƃ��������킪���y���Ă���B�~�M�g�[���������Ɠ��l�ɁA�[��̈����d�͂��g�p����B200V�̐[��d�͂𗘗p���邽�߂ɂ��̍H�����K�v�ƂȂ�B���̒~�M�g�[��͖�11�����璩7���܂ł�8���Ԃ̊Ԃɓd�C�G�l���M�[��M�G�l���M�[�ϊ����ē��ꃌ���K�ɂ��̔M��~�M����B�����A�~�M�����M����o����Ƃ������̂ł���B
�@�~�M�g�[����ɂ͔M��~�M�����邽�߂̏d�����ꃌ���K��30���܂��Ă���B���̃����K1������̏d����6�mkg�n�ł��邩��A30��180�mkg�n�̏d���ł���B����ɓS��➑́i�P�[�X�j������ƑS�d�ʂ�215�mkg�n�Əd���i�ʐ^1�`3�j�B�܂��A�O�`���@���A1076��672��250mm�Ɣ�r�I�傫���i�ʐ^4�j�B
�@�~�M�p�ɂ�200V�i��i����d�́F5,000W�j�̓d�C���g�����A�������邽�߂̃t�@����}�C�R���p�̓d�C��100V�ł���B���̂��߁A100V��200V�̓d�C���g���̂ŁA200V�̓d�C�H�����K�v�ɂȂ�B
�@�~�M�g�[��̉��x���ʂ͖ډ����肵�Ă���̂ŁA����܂Ƃ߂ďЉ�����Ǝv���Ă���B�ݒu���Ă���1�T�Ԃ��o�߂������A����܂ł̂Ƃ��돇���ŁA�ݒu�������Ԃ����Ȃ���Ȃ��������B����܂Ŏg�p���Ă������̂��邳����g�[���u�̒g�[�����Ȃ��Ă��ςނ̂ŐÂ��Ŏ��R�ȉ������ł���B���݁A���Ԃɑ����ďo����\�ȏ��ւƐQ���h�A���J�����ςȂ��ɂ��ĉ��x�𑪂��Ă���B�e�����ɂ͖{��Ƌ�ނ���R����̂ŁA�������g�߂邱�ƂɂȂ�̂ŁA���ԁA���ցA�Q���̉��x���ǂ�قǏオ�邩�̌��ʂ͒����ڂł݂Ȃ��Ƃ킩��Ȃ��B24���ԔM����M�������Ă���̂ŁA�ׂ荇�킹��3�̕������g�����Ȃ邱�Ƃ����҂��Ă���B
�@���̒~�M�g�[��̌��_�́A�~�̊Ԃ����g�p���邱�ƂɂȂ邩��ď�͎ז��ɂȂ邱�Ƃł���B���̔��ʁA�[��d�͂��g���̂ŁA�d�C�オ�����Ȃ邱�Ƃ����҂��Ă���B�y2010.12.21�z
�ʐ^1�F�����K�������Ă��Ȃ��~�M�g�[��̓����i�q�[�^�[�ƃ����K�j
�ʐ^2�F�����K���ςݏグ���Ƃ���
�ʐ^3�F�c��6�A����5�ςݏグ������
�ʐ^4�F�~�M�g�[��̊O�`�i1076��672��250mm�j
2010.12.28
|