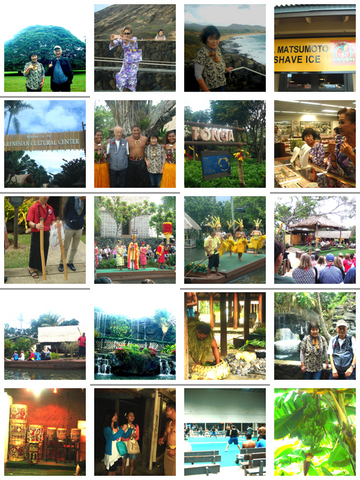ビーチに長々と横たわっている姿がとっても可愛らしいハワイアン・モンクシールとアホウ鳥が見られることを期待してカエナ・ポイントにやってきた(写真中上)。ハワイアン・モンクシールは、現在1,300頭から1,400頭しか生息していないと言われ、絶滅が危惧されている。このアザラシに会える可能性の高いところがオアフ島の最西端のカエナ・ポイントである。
野犬などの野生動物が入り込めないようにカエナ・ポイント周辺一帯に柵が張られてある。人が柵内に入るのには2重ドアのゲートを通過しなければならない(写真左下)。最初のドアを開けゲート内に入り、ドアを閉める。次のドアを開けて柵内に入るという2重ドアをくぐらないと入れないようになっている。このようにするのは、扉が1つだと開けたとたんに野犬などが瞬時に柵内に入り込むことを防止するためだという。
柵内に入ると広い砂浜だ。カエナ・ポイントへ向かう砂地の道両側にロープが張られてある。よく見るとロープの向こうにアホウ鳥が卵を抱いている姿があちらこちらに見られる。一羽のアホウ鳥がロープ際に座りこみ卵を抱いている。人間が近づいても驚かずにじっとしている(写真右中央)。アホウ鳥が飛ぶ姿を見たが、羽根を広げた姿は2mぐらいあるかと思われるほど大きい。
一方のアザラシは、見当たらない。誰かがあそこにいると指さすが岩とよく似ていて、アザラシだと特定するのは難しい。望遠鏡で覗くと、岩と異なり丸みをおびているのでアザラシであることが確認出来る。今日は一匹しか確認出来なかったが、多いときは何頭ものアザラシが砂浜に寝そべっているという。
カエナ・ポイントの近くに海岸に向けて設置されている用途不明の大きなコンクリートブロックが放置されている。同行した自然保護団体の人の説明によると、第二次世界大戦中、日本軍が接近することを早期に発見するための監視塔であったという(落書きされている写真左中央2枚)。
写真左上の景色を見ながら昼食をとり、歩いてきた道を逆に歩き、舗装道路沿いにある駐車場に午後2時ごろ戻った。自然保護団体の人が持参した冷えた缶ジュースが配られ、ジュースで乾杯し、各自が乗ってきた車で 帰路についた。長時間歩いた後であったので、ジュースがこれほど美味しく感じたことはこれまで経験したことがない。ともかく美味しかった。舗装道路を歩く10km・レース・デー・ウォークは、今年も無事に歩けた。山道あるいは今回のような不整道路を歩いたことがまずないMakikoは、10 kmの悪路を歩けたことに対し自分でも驚いている。その影には同行のハワイ大学研究員のJさんの支援と激励が大きい。Jさんに感謝する。【2017年12月18日】
平成29年1月3日(火) 自宅にて記す
|