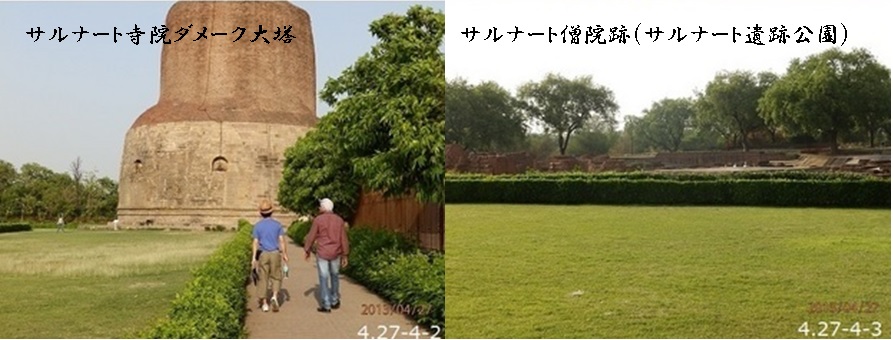�`���i���{�j�ւ̕����`���̓���(����5�j�����i����1�Ɠ����j�@�u�����`���̓����v�������������J�Ȍ�����������ƁA�u���{�֕������`�d����܂ł̓��v�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
�@�����@���Ƃ��������́A��g�ŏI���̂ł͂Ȃ��A�r���̓`���o�H���e���ꂽ�n��ɂ����ĐV���ȉ��߂������A�n��ɂ���ẮA���̐V�������߂̕����蒅����A�Ƃ��������������Ă���ꍇ�������A���g�̓`�d�ȏ�ɉe�����傫���Ȃ�悤�Ɏv���܂��B
�@
�@���������Ӗ��ł́A�ŏ��ɓ��{�ɓ`�d���������ȏ�ɁA��ɓ`�����Ă������`�̕���������Ղ���e���₷�������̐l�Ɏx������邱�ƂɂȂ�̂��Ǝv���Ă��܂��B
�@�܂��A����n��ŐM�Ƃ�����������e�����̂́A���̒n��Ɏ�e����镗�y����������Ă��邩��ł���A���̏����ɈӐ}�����Ɉ���Ă��ꂽ�l�������݂����\��������A���̎���́A�������`�Ƃ���鎞�_�ɔ�ׁA�ƂĂ��Ȃ��̂����m��܂���B
�@�����l����ƁA�V�������߂������㐢�����ł͂Ȃ��B�����啝�ɑk���ĕ�������e����镗�y�����������N�_�ƂȂ�o�����ɂ��ڂ�������K�v������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�@�]���āA���������߂ē��{�ɓ`�������ƌ����Ă���N��݂̂�����̂ł͂Ȃ��A����ȑO�ɂ����j�̕\�Ɍ���Ă��Ȃ��l�B�ɂ��`�d�A�����Ă���܂ł̌��`�Ƃ͈Ⴄ�`�d�o�H��S����B�ɂ��`�d���������\��������A����𑍍��I�Ɍ��Ȃ��Ɛ^�̕����`���Ƃ͌����Ȃ��l�Ɏv���̂ł��B�����͈ȉ���4�̏����ɏW���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
1.���`�������̐l�ɂ���Ďx������邱�ƁB
2.�`�d�o�H�͗��H�A�C�H���邢�͗��҂̃n�C�u���b�h�B�ꍇ�ɂ���Ă͊C�H�Ɠ������H�ł���^�͂��`�d�o�H�̈ꕔ��S�����Ƃ����낤�B�C���h�Ɠ��{�Ƃ̊Ԃɂ͗l�X�ȘA���H������܂��B
3.�`�d�̒S����i�ꍇ�ɂ���Ă͔��Q�ɂ���ē`����j�~���镉�̒S����j�����āA�V�V�n�����߁A�J�_�������ȒS���l���������ƁB
4.�`�d��ɂ��Ƃ��Ƃ������M�Ƃ̋����A�Z���Ƃ��������ݍ�p�̖��ɐ^�̕����`�����������B
�@�ƍl�����܂��B�����̗v�f���C���h�˂̒n�Ƃ��āA���{�ɓ`�d����܂łɁA��L1�`4���ǂ̗l�ɍ�p���Ă������A���肵�����������Ƃɂ܂Ƃ߂Ă݂����Ǝv���Ă���̂ł��B
�@���肵�������Ƃ́A������������C���h�A�X�ɂ͍����̓ޗǁA���s���̕����֘A���@��_�Ђ�q�ς��A���������ƂŁA�����ɂ��āA�u���O�ɋL�ڂ������͂��甲���]�L������A�ڍ��ɂ��ẮAWikipedia ���Q�l�ɂ����Ă����������肵�܂����B
�ȉ��ɑ區�ڂ��A33���A�@
���ڔԍ��@���ڃ^�C�g���@�@ �ŕ\���A
�區�ړ��ɒ����ڂ��@�@�@�@
�����ڔԍ��@�����ڃ^�C�g���@�ŕ\���A
�X�ɒ����ړ��ɏ����ڂ��@
�y�����ڔԍ��@�����ڃ^�C�g���z�@�\���܂���.
�@
�O��܂ł̑���Ƒ���́A�ȉ��̍��ڂɂ��āA�M�҂̎v���������Ƃɂ��ďЉ���Ă��������܂����B
�����͈ȉ������グ�܂����B
1)�������˂̒n�C���h�ł̎߉ށA���牤(�����傩����)�A�J�j�V�J���ƃq���Y�[��
2�j�ŏ��̓`���n�����A�W�A�̃K���_�[���A�匎���i�����������j
3�j�������c�_�A�w���j���i�ӂƂ��傤�j�x���`�A�n�c��⑾���]�̃��[�c�͛I��
4�j�匎���̌��A�|���N�̌��A�]�����@�����č�������̎q���A
5�j�V���N���[�h�i�J�V���K���A�T�(����)���A����(�������傤)���A�g���t�@���A����(�Ƃ�)
6�j�_���(����Ȃ傤)�̐M�@���](���傤����)�`�d�o�H
7�j�i�n��(����)�ɂ�鐼�W(��������)�����B�i�n��Ǝהn�䍑(��܂�������)
8�j�k���O���u�ɓo�ꂵ�������̔z���Ί�ɂ��āA�����Ĕ��n��
9�j�k���ƍY�B�����ԋ��R��^��
�����͈ȉ������グ�܂����B
10�j�������˂̒n�C���h�A�@�߉�(���Ⴉ)�A�A�A�V���J���A�B�J�j�V�J���A�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@11�j�������Y(���܂炶�イ)�A���}��(�ԂƂ��傤)�A���̒�q����(�ǂ�����)�A�@��(�ق�����)�A����(���傤)
12�j �Ӑ^(����)
13) �������Q�E�e��
14) �����A�V���A�S�ςւ̕����`��
15) �������̉����A�����Z�p�͕S�ρA�o����͍����
16) �O�`��䘌�
17) �����쒩�A���W�A��v�A���A��(����)
18) ���̍c��(�����Ă�)��F(�ڂ���)�A����A���ʉ��ł̘`���Ƃ̐ڐG
19)�@�����E�S�ρE�V���݂͌��ɘA�g�E�R���̂���Ԃ��A�S�ς�538�N�J�s�ȂǑ�ςȎ���
20)�@�`���i���{�j�ւ̕����`��
�@�@�y�Q�l.538�N�i��߁j���i�ȉ�Wikipedia���j�z
�@ �����`���A���`�A���I�ȐM�Ƃ��Ă̓`���z
�y���牤�R�Γ����z
�X�ɁA
��O������グ�����ڂ͈ȉ��̒ʂ�ł��B
22�j�ܑ�R
23�j�O�����猩���`��
24) ���̑����A�����`���A�n�c�鎀��̕��a��
25�j�|���N�A���q�g��
26) �����̐ΌA���@
�@�j�����@�����A
�A�j�_���ΌA���@
�B�j�ΌA�ɐ��ތ���Ő�l
�C�j�_���ΌA���@��O�A�̑���
�D�j�����Z�a�̗��j
�E�j�ΌA���@�̑��A���@�@
�F�j�c��ꑰ�̑����̗��j
�G�j�،��O���ɂ���
�H�j�����̓`�d�o�H�i���}���Ɠ����j
�����āA�O��
��l���ł͈ȉ��̍��ڂɂ��Ď��グ�܂����B
27) ���z�̒n�j�Ɨ��j�A�㒩�Ós
�@) ���z ���n��
�A�j����ΌA���@
28�j�����R�ΌA���@�@
29�j�g���t�@��
�@)�g���t�@���E�����̏�
�A)�g���t�@���E�A�X�^�[�i��Q
�B)�g���t�@���E�[�x�N���N�畧�� �@�}�j��
�C)�g���t�@���E�Ή��R�@
�����āA
�����܉��͈ȉ��̍��ڂ����グ��܂����B
30�j�呫�����@�i�����̐��E�ρj
�@�j�����Ō���“�O�E”�Ƃ�
�A�j�u�Z���։�v�̐��E�Ƃ�
�y�Z��B�S�z
�y�\������z
�B�j�k�R��
�C�j���̘Ȃ܂��A�����̋����@
31�j��X�̐M�ƕ����̓`�d���[�g�i�`���[�g�}�j
�y����1�z
�y����2�z
�y����3�z
�y����4�z
32)�قȂ�M�i�@���j�Ԃ̏K��
�@�j�}�j���i��7�j
�A�j�q���Y�[���ƕ����̊ւ�i��0�j
�B�j���]�i�_��j����
�C�j���ɗ��M��
�y�̓�(���傤�Ƃ�)�V�c�ɂ��_��i�_(����������)4�N�i770�j�̕S��
�@���ɗ�������(�ЂႭ�܂�Ƃ�����ɂ�����イ�����傤)�G�s�\�[�h�z
�y���ߍ]�s�Γ����G�s�\�[�h�z
�y����6�N�i1003�j����G�s�\�[�h�z
�y�d���A���牤���ɗ��a�Č��̍ޖG�s�\�[�h�z
�y�_������(������ɂ傤��)�A�������`���G�s�\�[�h�z
�y���d��/�������G�s�\�[�h�z
�y�������牤���s�G�s�\�[�h�z
�y���牤���̓��{�̎��@�Ƒ傫���قȂ�_�F�����Ɛ����̑Ώ̐��A�ۘO(����
��)�Ə��O(���傤�낤)�̕��݁z
30�j�呫�����@�i�����̐��E�ρj�@��
�u���O�u�ł̋C�����v��蔲���]�L���@�@�@
�ȉ������ʐ^�ԍ��͏�LURL�����Q�Ƃ̂��� �@���̒���,����܂łƓ��l�z�e���Œ��H���ς܂��A8:30�Ƀz�e�����o�������B15���قǂō������HG60�ɓ���A��H�呫(��������)��ڎw���B�^�]��̏�(���傤)����͎28�ł���A�Ⴓ����D�N�ł���B����̗��̍ŏ�����Ō�܂ł̃X���[�̉^�]��ł���B
�@���ꂾ���������𑖂��Ă��~�X�i���̊ԈႦ�j�������̂́A���\�\�K�����Ă���Ă���̂����m��Ȃ��B�L����Ƃ��B���������^�]��������Ă��ꂽ�p(�炭)����ɂ����ӂ��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B
9:56��G60���番�đ呫�����ցB����ɒn�ʂ̐F�͐Ԃ��𑝂��A���H�̑����ɂ���Č��ꂽ�f�w�͐Ԓ��Ƃ������ԐF�ł������i�ʐ^11.5 -1-1�j�B�r���A�Ԃ��߂₷���Ƃ���֒�Ԃ��Ă��炢�A�ԓy���̎悳���Ă�������B�@�����čX��15���قǂ��āA�ړI�n��тɓ������A�Ԃ���~��A�����Ɍ��������B�u���E��Y�呫�����E������Y�������V���}�v�Ə����ꂽ�ē��}���ڂɓ������B�@�ē��}�ł́A���ݒn����ŏ��̋���n��ƁA�悸���q�Z���^�[�n�悪����A�X�ɓ�ڂ̋���n�����Ƃ��납��呫�����@��ɓ���A�L�厛��A圣�����y�т����̕������������悤���B�����������̂�圣�������ƂȂ��Ă���B
���q�Z���^�[�n��̈�Ԗk�[�̐��ʂɎ��̎R��Ǝv���錚���������ꂽ�B20�i�قǂ̐Βi��o��߂��Ƃ���ɁA�ꕔ���ۂ⎂�q���x�����i�D��8�{�̐Β��Ɏx����ꂽ�傫�ȉ��������ꂽ�B�@������4�Ő��͒������̔���Ԃ�������Ă��邪�A�ʐF�͂����������Ȃ������������������܂��������Ă���B�ό��q�̕����̕����͂邩�ɍʐF�L�����B��̊z�ɂ͓V���呫�ƉE���珑����Ă����B����A���̌������͎R��Ƃ������ό��]�[���̌Ăэ����Ȃ̂��낤�B
�����đ��̐�ɉ˂��镝�L��100�����̒����̐���n��ƁA���@�����ꂽ�B���ꂪ�L�厛�Ȃ̂��낤�B�����ɂ��邷�ׂĂ̌������������ɂ͒��������ꉮ�Â���̉����\�������Ă��āA�F�ʂ��h��ł͂Ȃ��A���������������ł���B�����̎l�Ő��͓����I�Ȕ���͂Ȃ����A�������Ќ������̉����̗Ő��ɒ������鏬�����̎p�͌�����B����猚�����̗��j�͐��ł������B
���̎��@�̈�p���甲���o��������Ői�s�����E�������ƁA�Ȃ�̑��������Ă��Ȃ��ݕǁi�ʐ^11.5 -1-5�j���������B�傫�Ȑ��͐ς��������ŁA�n�w�͌���Ă��Ȃ��B���̑傫�Ȋ�̉��ʂ𗘗p���Đ̂̐l�����͑����@�����̂ł��낤�B
�����Ă���ɍs���ƁA�|�т̌�������10����ɁA�����Ȃ�݂̉��ɎO�w����Ȃ�����Q�i�ʐ^11.5 -1-6�j������ꂽ�B�ŏ�w�ɂ�10�̈ȏ�̒������镧���Q�����R�ƕ��сA���̑w�͍X�ɓ�w�ɕ�����A�s��̒��l���l����̐l�������������ԁA�����čʼn��w�ɂ́A�����|���ʎ��ʼn�������ɂ��Ă���l����������ꂽ�B
�ȉ��ɂ́A�����́A���Ɏ���̐��E�ςɂ��āA�W�����ꂽ������ʂ��Ď���ۂ�Ӗ��ɂ��ċL�����Ƃɂ��܂��B
�@�j�����Ō���“�O�E”�Ƃ��@
�@��
�u���O�u�ł̋C�����v��蔲���]�L��
�ȉ������ʐ^�ԍ��͍��LURL�����Q�Ƃ̂��� �u�O�E(����)�Ƃ͗~�E(�悭����)�E�F�E(��������)�E���F�E(�ނ�������)�̎O�̑��̂Ŗ}�v���������J��Ԃ��Ȃ���։鐢�E��3�ɕ��������́B
�~�E�Ƃ́A�����ɂ����鐢�E�ς̂Ȃ��ŗ~�]�i�F�~�E�×~�E���~�Ȃǁj�ɂƂ��ꂽ�������Z�ސ��E�B�O�E�̈�ŁA�n���E��S�E�{���E���C���E�l�E�V��i�_�j���Z�ސ��E�̂��ƁB
�F�E�Ƃ͗~�]�𗣂ꂽ����ȕ����̐��E�B���F�E�̉��ɂ���A�~�E�̏�ɂ���B���̐F�E�ɂ͎l�T�̎l�n�̏��T(������̂����̂�������)�A���T�A��O�T�A��l�T������A������߂���Ɩ��F�E�ɓ���B�V�E28�V�ɑ����B�F�͕����̋`�A���邢�͕��G�̋`�B
���F�E�́A�V���̍ō����Ɉʒu���A�~�]�������I���������z���A�������_��p�ɂ̂ݏZ�ސ��E�ł���A�T��(���傤)�ɏZ���Ă��鐢�E�B�ォ���z���z��(�Ђ����ЂЂ�������)�E�����L��(�ނ���䂤����)�E�����ӏ�(����
�ނւ�)�E�ӏ�(�����ނւ�)��4������B�v��Wikipedia�ɏЉ��Ă���B
�X�ɂ������������ƁA�u�呫�����z�}�v�Ȃ�Εǂɒ���ꂽ�ē��}�i�ʐ^11.5 -1-7�j�����ꂽ�B�����ɂ́A�M�쌧(�ǂ��Ȃ�)�A����(�ǂ���傤)���A�i�쌧(��������)�A�Z�i�����ɑv�j�����A���x���Ɉ͂܂ꂽ�呫���ɂ͕R���A�k�R���A���A�v5�������邱�Ƃ�������Ă���B
�ȏ�̓��A�R���A�k�R�������w���邱�Ƃɂ����B
�ŏ��Ɍ��ꂽ�̂���قǒ|�т̌������Ɍ����������Q�i�ʐ^11.5 -1-8�j�ł���A�����Ȃ�݂̗��ɂ́u�������揔����((�Ƃ��E�䂪�Ԃ���E�����������v�Ȃ镶���������Ă����B�u�(�䂪)�v�Ƃ̓��[�K�̂��Ƃ炵�����A�����̈Ӗ��͕�����Ȃ������B
�܂��A�ŏ�w�i���F�E�j�Ƒ��w�̐F�E�ɑ����镧���A�l���͋�F�ƐF�̊痿�����⊥�Ɏ{����Ă��邪�A�ʼn��w�̗~�E�ɑ����鑜�ɂ͐F�ʂ��{����Ă��Ȃ��B
�e�����ɂ́A�����������Δɒ����Ă��邪�A���̉𖾂͂��Ȃ����A�O�E���ꂼ��ɉ����āA��������l�X�ȏ�ʂ�z�肵�Ă�����̂Ǝv��ꂽ�i�ʐ^11.5 -1-9�`11.5 -2-9�j�j�B
�����čX�ɐi�ނƁA�߉ޟ��ϑ������ꂽ���A�����ɂ��H�����������B�����ş��ϑ��͉��x���������A����قǑ傫���̂͏��߂Ăł������B���̟��ϑ����߂���Ə�����ς��B
�A�j�u�Z���։�v�̐��E�Ƃ��@��
�u���O�u�ł̋C�����v��蔲���]�L��
�ȉ������ʐ^�͍��LURL�����Q�Ƃ̂����u�،��O�o��(�����傤����)�v�i�ʐ^11.5 -2-11�A11.5 -2-12�j�̎��́u�Z���։�v�̐��E�i�ʐ^11.5 -2-14�A11.5 -2-15�A11.5 -2-16�j�ł������B�u�Z���Ƃ́A�n���A��S�A�{���A�C���A�V�Ƃ����Z�̖��E���w���A�����ĘZ���։�Ƃ́A�O�����Z���̊Ԃ܂�ς�莀�ɕς�肵�Ė��ς̐��𑱂��邱�Ƃ������܂��B
�l�Ԃł��鎄�����̎������s���ĕ����Ƃ���́A���O�ɂ����Ď��������ׂ����J���}�i�s�ׁj�A���Ȃ킿�P�s�A���s�ɂ���Č��܂�悤�ł��B
��߂�Ƃ�����A�������d�˂��l�Ԃ���E�ɂ�����n�����S��C���̗̈�ɗ����A�}�f�Ȃ鐶���I�����l�Ԃ͐l�ԊE�Ƃ����̈�ɕ����A��葽���̑P�s���ׂ����l�͓V�E�Ƃ����̈�ւƏ����āA�����čĂѕ������ۊE�ł̐l�ԂƂ��Ă̐���������܂ł̊ԁA���ꂼ��̗쐫�̈�Ŗ��ς̐��𑗂�̂ł��傤�v��Wikipedia�ɏЉ��Ă���B
�����́u�Z���։��}�i���j�̑傫���́A�����A780cm�A��480�����A���䂫260cm�Ƃ�������Ȑ����ł���A90�̐l�����A24�̓��������A�����ėւ̒����ɂ̓A�j�b�J�i����j�̒�����Ŏx������Ă���B
�ւ͂U�O�x�Â�6�ɕ�������Ă��āA�e�����g���ɂ͐_���n�������������╨�̂����荞�܂�A�썰���אڂ��������g�̊Ԃ��ړ�����l������Ă��āA�����̋��`�ł���“�Z��B�S”�A“���ʉ���”�A“�\�����”��\���Ă���v�ƐΕW�ɍ��ݍ��܂�Ă���B
�y�Z��B�S�z�Ƃ́A�Z���i�����ɂ����Ė���������̂��։�Ƃ����A6��ނ̋ꂵ�݂ɖ��������E�̂��ƁB”�B�S�Ƃ͂��ׂĂ̌��ۂ͐S�ɂ���ĎY�o���ꂽ���̂ŁC�{���I�Ɏ��݂�����̂ł͂Ȃ��C�S�݂̂���̍����ł���ō��̎��݂ł��邱�Ƃ�������ł���B
�y�\������z��
�u���O�u�ł̋C�����v��蔲���]�L��
�ȉ������ʐ^�͍��LURL�����Q�Ƃ̂��� �ꂵ�݂̌����͖������n�܂�A�V���ŏI���Ƃ����A���ꂼ�ꂪ�����Ƃ��đ��݂Ɋ֘A����12�̈��ʂ̗��@��Wikipedia�ɏЉ��Ă���B“���ʉ���”�͌��킸�ƒm�ꂽ�l�Ԃ̋Ƃł���̂ŏȗ�����B
�����̍s�ׂ����V������Ɗ���������̂͂Ȃ����Ƃ����ƁA��Ɏ��������������������Ă��邩��ł���B�Ƃ��ɁA�������g�Ǝ����̏��L�ւ̂Ƃ��ꂪ�A���̗��R�ł���Ƃ�����B�@�܂�����������A����ƍb�h�ɐg�������߂����ʂ̐_�����i�����j��12�̂قlj����тŐ�����Ă���i�ʐ^11.5 -2-17�j�B
�\����������ꂼ��ގ�����_���B���A����Ƃ����ʉ�������{����G�[�W�F���V�[���B�悭�킩��Ȃ����A�����̐_�����̑O�ɘȂ�ł���ό��q�����������̂���ۓI�ł������B�����Ǝ����̏ꍇ�͂ǂ�ɑΉ����邩�A�����̋��Ɏ��u���Ȃ��������`������ł���ɈႢ�Ȃ��B
�����Ċ┧��傫�����蔲��������ɑ傫�Ȏ��q�̐���������������ΌA�����ꂽ�i�ʐ^11.5 -2-19�j�B���ɂ͑����̐����������u����Ă����i�ʐ^11.5 -2-20�`11.5 -2-23�j�B
�ΌA�ɂ͊O����̌����K�x�ɓ��荞�݁A�X�g���{�Ȃ��ŁA�ʐ^���B�邱�Ƃ��o�����B��������_�a�Ȋ痧�������������ł������B���O�܂ŁA�O�E�A�Z���A���ʂ̐_�����ȂǁA���낵����ʂ�����ė������߂����m��Ȃ��B
�ΌA����o��ƁA�����̂Ƃ���ɁA���ꂼ��ՂƋ��ɔ���̎p�ŏ���Ă���R�N�Ɠ��c�_�i�ʐ^11.5 -2-24�j�����ꂽ�B�R�N�͎肪3����A2�ŕ��������A��ō������Ă���p�ł������B�������߁A�R�̎��_�Ƃ����Ƃ��납�B
�����ŁA����܂Œ�����Ō��n�K�C�h�����Ă��Ă��ꂽ�����l�����i�ʐ^11.5-2-25�j�Ƃ͕ʂ�ł��������A�p����̍I���ȓ��{��ւ̒ʖ�ɂ���āA���̐��E��Y�̉��l�����������l�ȋC�������B
�R�����R����r���A���������p�i�܂��͘Z�p�j�l�d�̓��i�ʐ^11.5-2-26�j�y�ѐ��掛(�������ザ)�Ə����ꂽ��w�̂����i�ʐ^11.5-2-27�j�y�ђ�ߓa�A�����Đ����̉����������߂鐹��T�@(�������ズ��)�Ə����ꂽ�����i�ʐ^11.5-2-28�j��ڂɂ����B�E�E�E�����E�E�E�A
�B�j�k�R���@�@��
�u���O�u�ł̋C�����v��蔲���]�L��
�ʐ^�ԍ��͍��LURL�����Q�Ɖ������@�����āA���ԏ�ɖ߂�A�ԂŖk�R��(�ق���������)�Ɍ������A���n����14�F00�����������B���ԏ�ŎԂ������Ƃ����Ɋό��ē��}�i�ʐ^11.5-3-1�j���ڂɓ������B�قړ�k�ɍׂ��L�т��k�R���i����[����k�サ�Ă䂭�R�[�X�Ɍ��������B�ŏ��ɖڂɓ������̂͂ǂ����̍��̍����Ƃ��̉Ƒ��A�X�ɂ͔w���2�̂̐m�������z�u�����ΌA�i�ʐ^11.5-3-2�j�ł���܂����B
�����āA���Ɍ��ꂽ�̂��A��̕����ǖʑS�̂ɒ��荞�܂ꂽ�ΌA�i�ʐ^11.5-3-3�j�ł���A����܂Ō������Ƃ̂���ΌA���@�̌`���Ɠ����ł������B�@�ΌA���@�̏ꍇ�A�ΌA���ɂ����邱�Ƃ��ł��A��������A���̔w�ʂ��܂߂ĕ������V����q�ςł���ꍇ���������A�����̂́A����قǂ̍L���͖����A�A�̑O�ʂ���A���߂邾���ł������B
“��”��“�ΌA”�Ƃ̍��ق͂ǂ̗l�Ȃ��̂��A�R�ȏ�ɍ��ق����Ȃ��l�Ɋ������B�@�����ɓV�W�ƌ��w��������{���Ƃ��Ă̕����A������͂ޗl�ɔz�u������V��e����鏔������̒P�ʂƂȂ����A�i�ʐ^11.5-3-4�A11.5-3-6�j�����ꂽ�B
�����Đ��ʐF���c���Ă���A�i�ʐ^11.5-3-5�j�͐��ω��𒆐S�ɔ�V����A�����������k�ɒ����Ă����B���ʐF�͊��ɑ����̕��������������Ă��邪�A����������O�̂��̐��������āA�ǂ̂悤�ȋC�����Ŕq�������̂��낤���B���ʐF�p�ޗ��̓��r�X���Y�������m��Ȃ��B
�C�j���̘Ȃ܂��A�����̋����@�@��
�u���O�u�ł̋C�����v���
�����]�L���ʐ^�ԍ��͏�LURL�����Q�Ɖ����� ������ɂ��Ă��A�����k�R���́A�R��“�O�E“�A�Z��“�ƌ������l�̏��Ƃɑ�����߂�\�������̂ł͂Ȃ��A���̘Ȃ܂��J�ɍ���ł���悤�ł���A���S���Ĕq�ςł���̂ł���܂����B
�����Ď��Ɍ��ꂽ�Δ�i�ʐ^11.5-3-7�j�́A�����̋����������Ă��邱�Ƃ��A�������̒m���Ă��銿������ǂݎ��܂����B
�����ȒP�ʂ̐ΌA�ɂ́A�{����������A���̘e���ł߂�e�����A�����Ă���ɂ��̎��͂̓V�W�߂��ɔ�V�A�ΌA�ǂɒn���_�Ƃ����\�}�������Ɗ����Ă�����A�����ł͂Ȃ��A�{���͂Ȃ��A�����悤�ȕ����̕�F�������݂��ꂽ�P�ʂ̌A�i�ʐ^11.5-3-8�j��A�{������̂Ƃ����P�ʂ̌A�i�ʐ^11.5-3-9�j���������Ǝv���܂��B
���炭�A����i�����l���̕��ւ̑z���̈Ⴂ���o�Ă���̂��낤�B�������g���A�v�w���A�q�A�e���̉Ƒ��S�̂��A�ꑰ���ƁA���J���F��A�J��P�ʂ̈Ⴂ�ɂ���ČA���̌i�F���ς���Ă���̂ł��傤�B
����ƁA��i�҂̍��Y�͂̈Ⴂ���ܘ_�������ɈႢ����܂���B�V�W�ɂ��A�ΌA�ǂɂ������(������Ԃ�)�͂Ȃ��A�{���ɂ͌��w�̑���Ɉ֎q�Ƃ����ɂ߂ăV���v���ȌA�i�ʐ^11.5-3-10�j������������܂����B�@
�����Č㔼�̌A�͂قƂ�ǂ��ŏ��̌A���l�A�{�������āA��������͂Ŏ��e���Ƃ��Ă̐m�����A�{���̐�����������������g���ȂǁA�V�W�A�ΌA�ǂƂ����ԂȂ��召�̕����������Ƃ��ĕ���ł��܂����B
�@
�A���ɓ����Ĕq�����邱�Ƃ��\�ȂقǑ傫�ȌA�i�ʐ^11.5-3-11�`11.5-3-20�j���������������B���_�A�ό��q�����̗l�ȋ�Ԃɓ����Ĕq�ς��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�Ō��180�x�U��Ԃ�A�ό��q�p�ʘH�̎ʐ^�i�ʐ^11.5-3-20�j���B�����B
�����āA�k�R���i��̖k�ӂɎ���A�i����̏����Ȓr�̓�Ȃ𓌂̕����ɕ������ԏ�Ɏ������B���n����PM3:30���ł������A����̗��s�̍ŏI���̒n�A�d�c�s���Ɍ������܂����B��قǂ܂ŁA�ό����Ă����呫���������d�c�s�ɂ���A���̒��S���܂ł͎Ԃňꎞ�Ԓ��x�ł���܂����B
�ȏ�A�ΌA�Ɛ��͈قȂ���̂́A�Ƃ��ɁA�����܂��͕����̋������㐢�ɓ`���邽�߂̕������ɂ��āA�M�҂��T�K�������Ƃ̂���ΌA���@������@�ɂ��ďЉ�܂����B
�����ł́A�����̑��ɓ����A�A�����Č��݂͖w�nj`�Ղ��Ȃ����A�����ւƕϐg�����������A�ܓl�ē��ƁA���j�Ɏc��n���@��������A���ꂼ�ꒆ���̗��j�̉ߓx���ɓo�ꂵ�Ă��Ă���A�ƌ����܂����A�������j�������A�ƌ����܂��B
�X�ɂ́A�O���@���Ƃ��āA�C�X�������A�i���A�}�j���A���_�����̓V���N���[�h�Ƃ��������̌����H��`���āA���֓��ւƓ`�d���ē`�d�̓r���̒n��A�������[�̒n�ɓ`�d���A�X�ɂ͓��{�ɂ��Ñ���l�X�Ȍ`�ʼne�����y�ڂ��Ă��Ă��܂��B
�܂��C���h���˂̕����ɂ����Ă��A�������`�����i������������͏��敧���j�A�����Ėk�`�����i����敧���A�����j�A�X�ɂ͉_��Ȃ��璷�]�ɉ����ē��V�i�C���ݓs�s�֓`�d�����_�앧���⓯����敧���ɑ�����`�x�b�g����������A�`�x�b�g�����́A�_�앧���Ƃ����݂ɉe�����y�ڂ����ƍl�����܂��B
�M�҂͉_��ȍ�����嗝�A��]�Ȃǂ��x�ɘj���āA�K�₵�Ă��܂����A���̒n�̓c�����k�삷�鎞�̐g�̂��Ȃ����ς���A�l�X���b�����̃C���g�l�[�V������P�����̉������ɂ�����A���R�̕��i�������肷��ƁA���肦�Ȃ����ƂȂ̂ɁB ���������܂��O�́A���{�̂��Ă̓c�����i���������ދC�����ɂȂ����̂��v���o���܂��B���炭������DNA�Ƀ������C�Y����Ă���̂ł��傤�B
31�j��X�̐M�ƕ����̓`�d���[�g�i�`���[�g�}�j�ł́A�����ŁA��L�̎�X�̏@���ɂ��ĐG��Ă������Ƃɂ��܂��A
�}�ɃC���h�E�����E���{�𒆐S�Ƃ������ːM�E�O���M�E�y���M�E�`�d�M�ȂǂƂ��Ă܂Ƃ߂Ă݂܂����B���̓��A���]�i�_��j�����i��5�j�ƕ��_�M�i��9�C��10�j�͐����ȕ����ł͂Ȃ��X�I�ɕt�����ď̂ł��B
��1.�C���h���˂̕����i��0�j��4�̌`�ԂŒ����ɓ`�d�����B
��+���� �̓`���[�g�}�Ɏ������`�����[�g�ԍ��������Ă��܂��B
�y����1�z�K���_�[����匎�������o�Ē����k���ɓ`�d���A�V���N���[�h�ŁA�����O���M�Ƃ��Ẵ}�j���i��7�j�A���_�����i��8�j�A�i���A�L���X�g���A�C�X�������A���邢�͒����y���M�̓����i��������ܓl�ē����܂ށj��Ɖe���������Ȃ����敧���i�k�`�����j�Ƃ��āA���������ɓ`�d�i��1�j���čs���A���N�����o�R�Ř`���ɓ`�d������A���R��^�͂�쉺�����肵�ē��V�i�C���ݓs�s�̑h�B�A�Y�B�A���B�ցA�X�ɂ͑�p�◮�����o�Ę`���ɉe���i��4�j���y�ڂ����B
�y����2�z�^�C��X�������J���̓�A�W�A�����o�R�̓�`�i���(���傤��)�j�������_��ȂɎ���A�����ŁA�����̐M�ɍX�ɗאڂ����`�x�b�g�����i��3�j�̉e�������(���Ȃ���)�������̈ߐH�Z�����ƂƂ��ɁA���]������A���V�i�C���ݓs�s�̑h�B�A�Y�B�A���B�ցA�X�ɂ͑�p�◮�����o�Ę`���ɉe���i��5�j���y�ڂ����B
�y����3�z��A�W�A�̃^�C�A�X�������J�A�~�����}�[��`�����A�r��������V�i�C���ݒn��Ɋ�`���Ȃ���A���V�i�C���ݓs�s�̑h�B�A�Y�B�A���B�ցA�X�ɂ͑�p�◮�����o�Ę`���ɉe���i��6�j���y�ڂ����B
��2.�C���h���˂̕����́A�`�x�b�g�ɂ��`�����A��敧���ɋ߂��Ɠ��̑h�B�A�Y�B�A���B�ցA�X�ɂ͑�p�◮�����o�Ę`���ɉe�����y�ڂ����B
�y����4�z�C���h���˂̕������`�x�b�g�ɂ��`���i��2�j���A��敧���ɋ߂��Ɠ��̐M�����グ�����A����I�ɂ͂���3�܂ł̓`���ɒx��ă`�x�b�g�œƎ��̐M�Ƃ��ċ��`�̐i���𐋂��A�Ɨ������d���`�x�b�g�������`�����A����Ɏ����Ă��邪�A�`���ւ͉����A�e���͂قƂ�ǂȂ��B
32)�قȂ�M�i�@���j�Ԃ̏K�� �`���ɂ͓y���M�Ƃ��Ĕ��S���_�A���_�����̉e�����������Ƃ̌���������_���A�X�ɂ͍��c�����C�Ɉ��ޓc���_�Ђ┪�����Y�`�Ɠ��������J�镐�_�M�i��10�j�A�������^���̊w��̐_���J��V���_��
���̊w��̐_�M�_�Ёi��11�j�A�X�ɂ͊C�����_���J��C�_�M�_�Ёi��12�j�i�@���O���_�A�����������邪�A�����ł����_�M�͂���A�O���u�ł̉p�Y�։H�i��9�j�͒����e�n�Ɏ߉ނ�V�q�ƂƂ����J���Ă���Ƃ�����������邱�Ƃ����������A��������ɑ���ꂽ���̂������B�֒�_�����l�ɂ����邪�A�ό����l�ł���A�M�I���l�͏��Ȃ��Ǝv���B
�ȏ�̓��A�����̃u���O�u�ł̋C�����v�Ɏ��グ���u
�}�j���v�i��7�j�ƁA�q���Y�[���ƕ����̊ւ�i��0�j�ɂ��āA�ȉ��ɔ����]�L���ďЉ�܂��B
�@�j�}�j���i��7�j
�yD3-4:�g���t�@���E�[�x�N���N�畧���z�@��
�ʐ^�͍��LURL�����Q�Ɖ�������
�k������11�F00�����߂��A�[�x�N���N�畧���̓�����̒��O�̂Ƃ���̌��i����Ή��R(������)�̘[�Ɉʒu���邱�Ƃ�������i�ʐ^��1�j�B�����߂��Ō���ƉΉ��R�̏c�Ȃ�f�w�A�����ĉɏĂ����悤�ȐF����O�Ɍ�����B
�[�x�N���N�Ƃ����̂́A�E�B�O����Łu�������ꂽ�Ɓv�̈Ӗ��炵�����A�m���ɊO�ς̑��`����������i�ʐ^��2�j�B6�`14���I�ɑ���ꂽ83�ӏ��̐ΌA������A40�ӏ��ɕlj悪����Ƃ̘b�ł������B���̂����̐��ӏ���q�ς������A�C�X�������k�ɂ���Ĕj�ꂽ��ʂ̖������̎p�͖��c�ł���B�E�E�E�����E�E�E�A�܂������y���ɑk�邱��7���I���ɂ̓}�j�������̒n�g���t�@���ʼnh���A���̐畧���ɂ̓}�j���ΌA������ꂽ���A�}�j���k���g���t�@���ł̍ő吨�͂̕���������Ɏ���A�}�j���ΌA�͕����ΌA�ւƑ��肩����ꂽ�Ƃ̂��Ƃł���B�}�j���͕����Ƃ̐ړ_�������A�u�b�q���d��v�A�u�E�������Ȃ��v�A�u���҂��d��v�A�u������Ȃ݂�v�Ƃ��������ʂ̋��`�������Ă����Ƃ̂��ƁB
�lj�͐��E�B�O����������i9�`11���I���j�̂��̂������A�Ԃ���ɂ����E�B�O�����{�l��`�������̂������A���̓��e�͕����̑��o�T�̈�������A�o�ω�A�畧���`����Ă���Ƃ̂��ƁB�A�X�^�[�i�Õ�Q�̕lj�ɁA�Ԓ��}���`����Ă����̂��v���o�����B
�[�x�N���N�畧���͑��z��������ƁA���ԐF�ɐ��܂�i�ʐ^��3�j�B�w�i�̎R���Ԃ��ł��t���B��ꎞ�Ԋϗ����A�A�r�ɂ��i�ʐ^��4�j�B
�A�j�q���Y�[���ƕ����̊ւ��i��0�j
�u4/28�i���j
�y�i���X�@�K���W�X�́i����2�j�v���B�u���O�u�߉ނ̐��U��K�˂āv�̕\�����g�킹�Ă��炤�ƁA�u�K���W�X�́i�K���K�j�́A�C���h�ōł����Ȃ�͂ŁA�S�q���h�D�[���E�̐_���Ȑ��̌����ŁA��Ȃ鏗�_�Ƃ��Đ��߂��Ă��܂��B
�q���Y�[���k���������M���Ă���ʏ��̂ЂƂɁu�K���K�̐��Ȃ鐅�ş�������A������ߋƂ͐��߂��ď��ł��A���@�[���[�X�B�[�Ŏ���ň�D�𗬂��A�ꂵ���։��E���邱�Ƃ��ł���v������A�N�ԕS���l������҂̒��ɂ́A���̒n�Ŏ��ʂ��Ƃ݂̂�ړI�Ƃ���l������������܂���B�v�ƂȂ�B
�����͟���������l���������łȂ��A���҂�䶔��ɕ�����i�Α���j����������A�͂Ɉ�D�����łȂ���̂��̂��̂�����Ă����肷�邱�Ƃ�����A�ƕ����Ă��������ɁA���C��������ۂ��������B
�������A�K���W�X�͂̐�ׂ�ɏo�����A���̈ӎ��͖����Ȃ�A�ނ���C���̂��A���l�ȋC�����ɂȂꂽ�B�E�E�E�����E�E�E�B�q���Y�[���͐M�҂̐��ł́A�L���X�g���A�C�X�������Ɏ����ő����B�����͂ǂ��������Ƃ����ƁA�n�c(����)�ł���߉ނ́A�q���Y�[���̎O��_�̈�ł��郔�B�V���k�_��9�Ԗڂ̉��g�Ƃ���Ă���B
�C���h���@25���ɂ́A�i�q���h�D�[�����番�h�����ƍl������j�V�N���A�W���C�i���A������M����l���L�`�̃q���h�D�[�Ƃ��Ĉ����Ă���B�����������Ƃł���A�����k�����q���Y�[���k�̕������|�I�ɐM�҂̐��������Ȃ�̂����R�ł���B
�q���Y�[���̎O��_�Ƃ����̂́A���E�ێ��̐_�A�����̐_�A���_�K���[�_�ɏ�郔�B�V���k�_�A�n���Ɣj��̐_�A��蕨�͉����̃i���f�B���̃V���@�_�A�����āA���E�n���̐_�A�����n���T�ɏ�����V�l�̎p�ŕ\�����u���t�}�[�_�ł���B�O��_����������g�╪�g�����B
�����ŋg�˓V�Ə̂���郉�N�V���~�[�́A�߉ނƓ��l�A���B�V���k�_�̉��g�ł���A�����ŁA�单�V�Ə̂����}�n�[�J�[���́A�V���@�_�̉��g�A�ٍ��V�Ə̂����T���X���@�e�B�[�́A�u���t�}�[�_�i���V�j�̐_�܂ł���B
�X�ɁA����V(���Ă�)�i���V(���傤�Ă�)�j�́A�V���@�_�̎q���ŏۂ̓������_�A�l�ɏ��B�x�Ɣɉh�A�q�b�Ɗw����i��K�l�[�V���A�����ł͒�ߓV(�������Ⴍ�Ă�)�Ə̂����C���h���ȂǁA�����ŁZ�Z�V�Ə̂���镧�́A�w�ǃq���Y�[���̎O��_�₻�̐_�܁A����сA�����̕��g�A���g�A�X�ɂ́B3��_�̉��g�Ƌ��Ɋ���_��A3��_�̎q�_�ȂǂɑΉ����Ă���B
�܂��A�g�̂̑傫�������R�ɕς����A�O�������ŁA���B�V���k�_�̉��g�ł��郉�[�}�������鑷���̌��ɂȂ����ƍl������n�k�}�[�����q���Y�[�_�̈���ł��邪�A����ɑΉ����镧���́Z�Z�V�͕��������Ƃ͂Ȃ��B
�Z�Z�V�ƌ����悤�ɁA“�V”�̕����̂����́A�@�����F�ƈقȂ�A�l�ɒ��ڍ�p����̂ł͂Ȃ��A�@�����F�̊����������鑶�݂Ȃ̂��������B�q���Y�|���ɉ����āA���B�V���k�_��9�Ԗڂ̉��g�Ƃ���Ă���߉ނ̊������ז����鑊��Ƃ͐키�K�v������B�]���āA�Z�Z�V�̌��c�͑����̏ꍇ�A�Z(��낢)��
�g�ɒ����A��ɂ͕���������Ă���ꍇ�������̂��낤�B
�@�E�E�E�ȉ��ȗ��E�E�E�@�@�@�@
�B�j���]�i�_��j�����_��Ȗ����́A���{�l�̃��[�c�Ƃ����������邭�炢���{�Ƃ̋��ʓ_�������B�i�n�ɑ��Y�́u�X�����s���A�_��̓��v�ʼn_��Ȃ̗��j�A�n�j�A�������A���y�A�M�Ȃǂɂ��āB��80�łɘj���āA�L�ڂ��Ă��܂��B�M�҂͏��߂Ẳ_��ȗ��s�O�ɁA���̒��ɖ�80�łɘj���ċL�ڂ��ꂽ�_��Ȃ̓�����
���āA�C�ɂȂ鍀�ڂ��A�\�K�̂���ō��ړ��e��A�܂Ƃ߂��]�L����
������
�u���O�u�ł̋C�����v�ɋL�ڂ��Ă���̂ŁA�����ł��̎�ȍ��ڂ��ċL���܂��B
�y�[�W �i�n�ɑ��Y�@�u�X�����s���@�_��̓��v�����]�L
153 �_��ȁ@�@�R���J�����^�C��n��`�x�b�g�n�̐l�B�̓V���ł�����
155 ����̂���@�@�M�B�ȁA�_��Ȉ�т��u����v�ƌĂ�ł���
����H�ׁA������h�g�ŐH�ׂ�
�_��ȁ@���]�̏㗬�@�]��܂ʼn����Đ��͂��������̂��A���Ɖz
163 ���̎g�҂ɑ��āA滇����㳂́u��Y����v
177 �����l�i���R�j�@���i���g���ĕ��w�����邱�Ƃ͊����������̓���
179 ��ٕ����͈��Ɛ���������Ƃ��A���������A����������ێ悵�A�`�x�b�g�����A�^�C��n�����A�C���h�����̉e��
����A��ٍ��́u�f�ׁv�̌㉟�����A���ɂ��ނ����˂Ȃ�
187 ���R�ɓ��ρi�����̎��j�@�R�x�M�@���A�W�A�Ñ�ɋ��ʂ����M�����ŁA���{�̌��n�_���Ƃ������W?
211 �_��̏����@�@�@�����i�\���X���j�A��蘑�i�\�����j�@�@�L�m�R��蘑�A�ہ@�@�@�@�����ہi�X�������W�����j
214 ����@�_��Ȃ������A�͔|�̖{��
217 22�̏��������@���{��앶���̑c
�_�얯�������فF���t�@����̏o�y�i�@�@���Z�p�̌����͈�쏭��������
�_�얯�������فF�Â�����@���ΎR�Õ��Q����̏o�y�@�L�k���ʉ݁A������钙�L��𑈂���i����������Ă���
222 �_�얯�������فF�G�Z�@�ւ܂��ėx���l�@�M�@�u�U�y�v�A�u�Ίy�v�@���{�́u���y�v�ɓW�J�m�ޗǎ���j
223 ����i�����j�F�@�@�Ӎ��i������j�G�k���A�C�����n�����̍�����@���̉e���ŁA�y�ԂɈ֎q�A�e�[�u����u������
229 �������̑f�`��������L�͂ȗv�f�Ƃ��ČÑ�㳑����������̂ł�
�C���͉_��Ȃ�����300���l�@���̒��ɃT����
�u�q�{�n�̃`�x�b�g���������ẮA�قƂ�Lj�얯���ł���A���܂���������Â��Ă���B������H�ׁA������h�g�ŐH�ׂ�B���̖��������{�l�Ɏ��Ă��邱�ƂŁA�_��Ȃň�삷�鏭�������������ǂ��̐�c�̈�h�ł͂Ȃ����A�Ƃ��������́A����ɂ����{�̑����̕����l�ފw�҂��疣�͂������ď������Ă��邩�A�x������Ă���B�v�ƌ����Ă��܂��B
���̉_��Ȃ��璷�]��`���ē��V�i�C���ݓs�s�Ⴆ�Αh�B�ɂ܂ŗ��āA��������́A���V�i�C�ɂ����Ėk�������ɊC�H�ړ�����A���{�ɗ��邱�Ƃ͕s�\�ł͂Ȃ��B���邢�́A���V�i�C���݂ɏo��O�ɏ�����ɂ���āA�Y�B�╟�B�Ɏ���A��������A��p�A�������o�ĊC�H�`���܂œn���Ă����_��l��A���̒������n���璷�]�֒H��A��������͓����o�H�Ř`���Ɏ������l�����������ɈႢ�Ȃ��B
�ނ�͉_��Ȃ̈ߐH�Z������M���ꏏ�ɒ��]�o�R�Ř`���ɂ����炵���\���͑�ł���B�M�͖k�`�ƌ������́A�^�C�A�~�����}�[�A�x�g�i�����̓�A�W�A�����o�R�̓�`�����ɋ߂��Ǝv���܂��B
�]���ď��敧���I�ȋ����������`�����A�Ñォ��A�����Ɍ����������ȓI�ȋ������`�����ꂽ�A�ƍl���ėǂ��̂��낤�Ǝv���Ă��܂��B
�������V�i�C���݂̔J�g�s�ɂ��鈢�牤����K�ꂽ���Ƃ��A����܂����A���������n��ɂ��鎛�@�ɔ�ׂȂ�ƂȂ��Ԑ��F�̌��F���g�����Ȃ܂��Ƃ������A���F�̒��x���ア�z�F���g���Ă���l�Ɋ������̂��o���Ă��܂��B
���牤���͕��ɗ��M�̃��b�J�ł���A����Ɋւ��Ă̓��{�Ƃ̌𗬂̃G�s�\�[�h������̂ňȉ��ɏЉ�܂��B
�C�j���ɗ��M���@����(�A�V���J)���M�Ɠ��{�̊W�ɂ����Ď��̋L�������o�Ƃ��Ă悭�p�����܂��B
�@�̑�ƔN�ԁi605�`17�j�ɘ`���̊��l���(�������傤)�����w�ɗ��Ă���A���O�i�����ȊO�̊w��ƕ����j�ɂЂ낭�ʂ����B���5�N�i631�j�ɖ{���̓���7�l�ƂƂ��ɋA���̍ۂɁA�s�̑m�����`���̕��@�ɂ��Đq�˂����A���̎��Ɉ��牤�̔����l�瓃���S���E�ɋy�Ƃ������A�`���ɂ����牤�������邩�Ǝ��₷��ƁA�u�䂪���̕����ɋL�ڂ͂Ȃ����A�y�n���J�����邽�тɉ��X�Ƃ��ČÓ��̗��(�ꂢ��)���o�Ă���A���ꂪ��������đ����̊�����邩��A����̂��낤�v�Ɠ����Ă���i�w�@�����((�ق�������)�x����38�A�h���ё�(�����Ƃ��ւ�)35�V2�A�̓���(���Ƃ���)��6�j�B
�@
�O�m12�N�i821�j5��11���ɔd�����ō�3��8���i114cm�j�̓��������@����Ă��邪�A�����m�����u���牤���̑��ł���v�Əq�ׂ��Ƃ����i�w���{�I���x�O�m12�N5�����ߏ��j�A�܂����2�N�i860�j8��14���ɎQ�͍������S���̏��R�̒��ŏo�y��������3��4���i102cm�j�̓��������コ��Ă��邪�A��������牤�̕���Ƃ��ꂽ�Ƃ����i�w���{�O����^�x��4�A���2�N8��14���h�K(����ڂ�)���j�A
���̂悤�ȓ������@�̗�͌Â�����L�^������A������(�����ӂ���)�����ɍۂ��ē��������@����Ă���悤�Ɂi�w�}�K���L�x��5�A�V�q7�N����17�����j�A���@�����ɍۂ��ē����̔��@����Ƃ��ꂽ��Ƃ��āA���ɂ͐ΎR�������邪�i�w�ΎR�����L�x�j�A���牤�Ƃ̊֘A���Ȃ��ꂽ�͕̂�������O�I����̂��Ƃł���A���̔��[�͓ޗǎ������ɂ������B
�@���{�ɂ����Ė{�i�I�Ȉ��牤�ɗ��M�̌_�@�ƂȂ����̂��A�V������6�N�i754�j�̊Ӑ^�̓��{�s���ł���B�ނ̐����������̒��ɔ@�����ɗ����O�痱�A���牤���l�̋����̓������邪�i�w����a�㓌���`�x�j�A�O�q�����悤�ɊӐ^�͈��牤���ɐ������Ă���A���ꂪ���牤���l�̓������Ɍq�������Ƃ݂���B
�Ȃ��B�V��3�N�i731�j8��10���Ɉ��牤�o�܊��̎ʌo���s�Ȃ��Ă��邪�i�u�ʌo�ژ^�v���q�@�������X�C�\���O�q����{�Õ����ҔN7�r�j�A�c��Ȏʌo���Ƃ̈�Ƃ݂�ׂ��ŁA�K���������牤�ɗ��M�Ƃ̊֘A�����o������̂ł͂Ȃ��B
�y�̓��V�c�ɂ��_��i�_(����������)4�N�i770�j�̕S�����ɗ���(�����)�������ƃG�s�\�[�h�z�܂��̓��V�c�ɂ��_��i(������)�_(����)4�N�i770�j�̕S�����ɗ������Ƃ����牤�����l�瓃�Ƃ̊֘A���w�E�����B
�y���ߍ]�s�Γ����G�s�\�[�h�z�@���牤�����ŏ��ɖK�ꂽ���{�l���N�ł������̂��s���ł���B�����̐��b�ł��邪�A���(���Ⴍ���傤)�i962���`1034�j�͈��牤�������炵�Ēr�̑O�Ɏ���ƁA���m������{�̋ߍ]�������S�̓����r�Ɍ����ƂƂ��ɕ�����ł���ƌ����A���̂��Ƃ���Ƃ͏����L���A���ɓ���ĊC�ɕ����ׂ��B�O�N��ɌF��R�ߒq�Y�ɒ��݂��A��������M�i942�`1017�j���J�����Ƃ����i�w�k���E�t�W(������イ�悤���イ)�x�Γ���(�����ǂ���)�ċ����L�j�B
�y����6�N�i1003�j����G�s�\�[�h�z���ۂə���6�N�i1003�j�ɁA���{���̑m��Ƃ����M�́u�V�䋳��v�����ړ�\�����v�����c���m��i960�`1028�j�̂��ƂɌ��킵�Ă���i�w�l�����ҋ��s�^(�x����1�A���ҔN���A����6�N���j�A���c���Ƌ߂��������牤���̂��Ƃɕ������\�������邪�A���̐��b�������Ď�Ƃ����牤���ɏ��炵���؋��Ƃ���̂́A������������������B
�y�d���A���牤���ɗ��a�Č��̍ޖG�s�\�[�h�z�O�q�����悤�ɁA���牤����\�E(�̂��ɂ�)�̒�q���K��Ă��邪�A���̌���{�ɂ����鈢�牤���M�ɏd��Ȗ������ʂ������̂��d���i1121�`1206�j�ł���B
�d���͓��v���Ĉ��牤����K��Ă���A�A����̎��i2�N�i1183�j����24���ɋ�������i1149�`1207�j�Ɉ��牤���̗l���ƌ��n�̐M�ɂ��ďq�ׂĂ���i�w�ʗt�x���i2�N����24�����j�A�܂����h�̍��̍ޖ𑗂��Ĉ��牤���ɗ��a�Č��̍ނƂ��Ă���i�w�얳����ɕ���P�W�x�j�B
�y�_��(������)����(�ɂ傤��)�A������(������̂������)�`���G�s�\�[�h�z���͖@�c���������ɗ�2,000���̂����A1,000���͈��牤�����瓾�����̂ł���A�Ȍ�_������i���v�N�s���j�A�������i1118�`81�j��ɓ`�����ꂽ�Ƃ����i�u���ɗ������}�v�Ӌ{�_�Ёj�B
�y���d��/�������G�s�\�[�h�z�܂����d���i1138�`79�j�͈��牤���̐و������ɋ�1,000������i�����Ƃ����i�w���ƕ���x����3�A���n�j�A����4�N�i1216�j6��15���Ɍ������i1192�`1219�j�Ɩʉ���a���i���v�N�s���j���A�����̑O�������牤���̒��V�i�Z���j�ł������Əq�ׂĂ���i�w��ȋ��x����4�N6��15�����j�B
�y�������牤���s�G�s�\�[�h�z�����i1200�`53�j�͉Ò�16�N�i1223�j�H�ƕ�c���N�i1226�j�ĂɈ��牤���ɍs�������A���L�̕NJԂɐ��V���n�O�\�O�c�̕ϑ����`����Ă���̂����Ă���i�w���@�ᑠ�x�����j�B
���{�o�S1207�`98�j���~�S10�N�i1250�j���牤�R�ɕ�����2�N�ԑ؍݂��Ă���i�w�h��J�R(���イ�ق���������)�@���~�����t(�ق��Ƃ�����݂傤������)�s���N���x�~�S10�N�M�����j�A�Ȍ㒆���ɓn�����T�m�͈��牤���ɑ؍݂���҂����������B
�y���牤���̓��{�̎��@�Ƒ傫���قȂ�_�F�����Ɛ����̑Ώ̐��A�ۘO�Ə��O�̕��݁z�K�ꂽ���牤���̓��{�̎��@�Ƒ傫���قȂ�_�����邱�ƂɋC�������̂ŁA�u���O
�u�ł̋C�����v���甲���]�L���ďЉ�����Ǝv���܂��B
���ʐ^�ԍ��̓u���O�L�ڂ̂��̂ł��B�u�E�E�E�A�������A���̐����Ɠ����̃A���o�����X���͈�̉��Ȃ̂��낤�A�����̊ԈႢ�����m��Ȃ��A�Ǝv���A�E�F�u�ŃL�[���[�h���������Ă݂��B����������A维��S�ȂȂ钆����E�F�u�ɁA�u������\�ܔN�i1365�N�j���I砖���C��36�āC��层�Z�ʁB东����层���p�C1995�N�v�H�v�Ƃ��邱�Ƃ����������B
�����A������7�w�Z�ʁA������7�w���ʂł�����20�N�قǑO�ɏv�H��������Ȃ̂ł���B�F�͐��������������F�A�������������F�ōŏ��Ɍ������̂Ɠ����ł���B
�x�d�Ȃ�ЁA���ׂ錚�z��i�����ҁj�̎v�z�ɂ���ďC���̂�������قȂ�̂��낤�B�������A�ٍ�����̗��s�҂������҂̎v�z�𐄑����邱�Ƃ͕s�\�ł���A���F�����W���Ă����p�i�ʐ^10.31-7-1�j�ɂ��������̓��F���������i�ʐ^10.31-8-1�j�ł���A�����ɂ͋��s�J�ɋP�������̕������z�u����Ă����i�ʐ^10.31-8-3�A8-4�j�B
�@���A���F�����W���Ă����p�i�ʐ^10.31-7-1�j�ɂ���X�ɂ�����̓��F�����牤���ۘO�i�ʐ^10.31-8-2�j�ł���A�ۘO�Ƃ͏�s�A�s�s�A�@���{�ݕ~�n���ȂǂɌ��Ă���A���ۂ�ݒu���邽�߂̌����ŁA���ۂ�炷���Ƃɂ���āA�����A�ً}���Ԕ����̓`�B�Ȃǂ̖������ʂ������B
������O�͎��@���ɂ����Ğ�����݂��A����������{�݂ł���A��������������͋��ʂ��Ă���B���̎��@�ɂ͗��O������A�s�v�c�Ȉ�ۂ����B�E�E�E�ȉ����B
�@�@�@�@�@�@�@
��5��@���@��6��ɑ����@