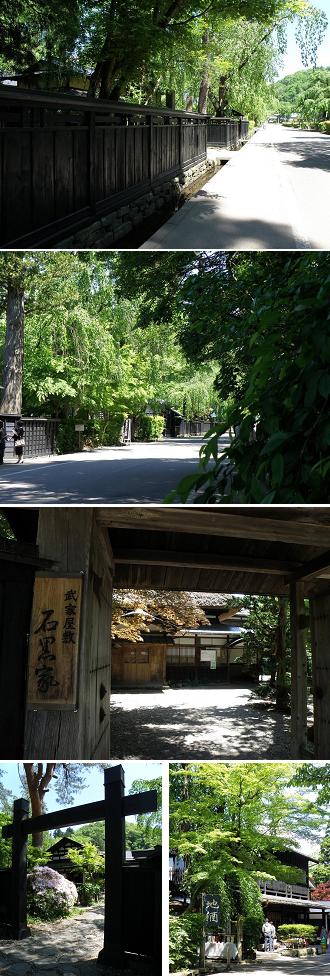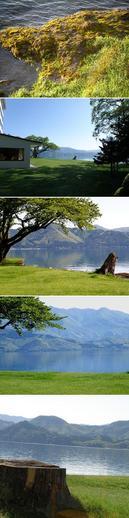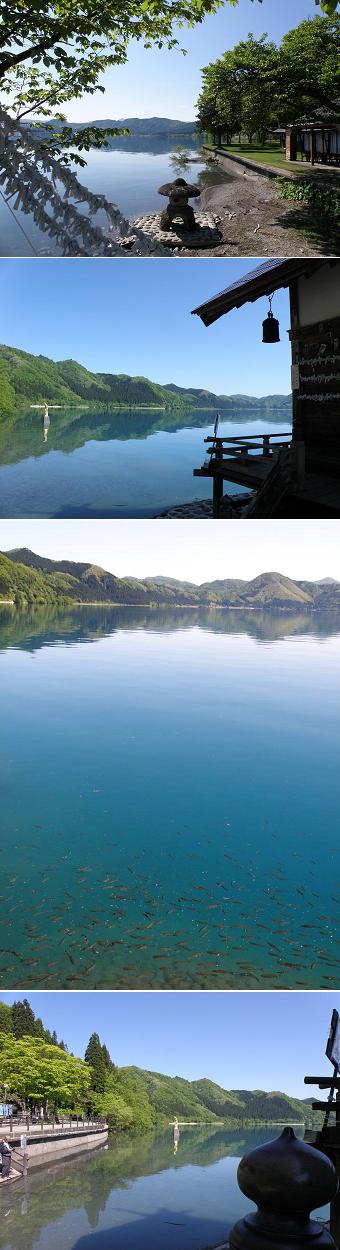前の話<<< 66.日本人と中国人 >>>
3)日本人と中国人(3)
その端著ととして、
「ところで、先ほど、東伝さんという人の名前がでましたが、どなたですか?」と思い切って聞いてみた。
「東伝さんは自分の人生では大切な恩人で、私の人生の指針を与えてくれたといっても良い両親の次に大事な人でした。日本へもその人の先導がなければ来られなかったと思います。」
「今もお元気なのですか?どちらにお住まいですか?」
「私が中国で結婚するまではいつも近くに居てくれましたが、二度目に日本にやってくる直前に主人とともに交通事故で亡くなりました。そのことを想い出すと今でも悲しくて仕方なくなります。」
「そうでしたか。悲しい出来事を思い出させて申し訳ありませんでした。でも、その東伝さんについてもう一つだけ聞かせて下さい。東伝さんの出身地は中国のどのあたり?」
紅蓮は、「崑崙山脈の麓の・・・」と言いかけて、「本当はご本人にはっきり聞いたことがないので、結局どこか私にもわからないのです。ただ亡くなった主人を私に紹介してくれる時、『自分と同郷の、』と言っていたので、崑崙山脈の麓のホータンと勝手に思い込んでいました。
主人の出身地がホータンから、白玉川を少し遡ったところなので、そう思ったのです。」
「そうでしたか、そういうことでしたら誰だってそう思いますよね。」
「ええ、でもそれまでは、東伝さんは、よく私に崑崙の仙人のお告げだと言って、いろいろな話をしてくれましたが、その話ぶりからは、東伝さんから見ても崑崙というのは仙境の地で、そこが出身地という感じは受けなかったのです。主人と私を一緒にさせるための嘘だったかも知れなかった、と最近になって思うようになったのです。それに東伝さんの葬儀に見えた東伝さんの息子さん達の話では、崑崙ではなく四川省か雲南省という感じでした。」
「そうでしたか、そういうことでしたら誰だってそう思いますよね。」と言いながら、自分も訪問したことのある四川省の話が出てきたので、記者は我然勢いついてしまった。
実は記者は崑崙山脈とかホータン、あるいは白玉川という川の名前が出てきてもどのあたりかさっぱり検討もつかなかったのである。新聞記事には座標があって、その原点がわからないと記事を書きようがないのである。
その座標原点の候補となりうる地名が出てきたので、これからが取材といえる、と思うことにした。そしてインタビューを続けた。
「先ほど、もう一つだけと言って質問しましたが、構わなければもう少し話をつづけさせてもらえませんか?」
「構いません。私もずっと胸のうちに暗くしまっていたので、いつかはそれを吐き出して、明るい気持ちになれたらと思っていました。聞いていただければ知っていることは何でもお答えします。ここのママさんも時間を気にしないで、記者さんと話をしていて良いと言ってくれていますので。」
そこへタイミング良く、店のママさんが二つのコーヒーカップを載せたお盆を捧げ持つ様にして記者と紅蓮が座っているテーブルに近づいてきた。
「西畑さん、紅蓮さん、コーヒー如何ですか?話が弾んでいたようなので遠慮していたのだけど喉も渇くでしょうと、気を利かせたつもり。」と言って、コーヒーカップをテーブルに置いて立ち去ろうとした。
西畑は、「ママさんも一緒に話に加わりませんか?いいでしょ紅蓮さん?」とママさんと、紅蓮をかわるがわる見つめながら哀願するような表情を見せながら話しかけた。
紅蓮は、「この人、西畑という名前なのだわ、ママさんに話しに加わってもらえば、もっとリラックスして話すことが出来そう。大歓迎だわ。ついでに、あの四面聖獣銀甕に加わってもらえれば、完璧なのだけれどね。」と独りごちた。
ママさんは、「あら西畑さんありがとう。でも邪魔しちゃ悪いもの、遠慮しておく」と言って、カウンターの方へ戻って行きそうになった。ところが途中で急にUターンして二人の方へ戻ってきた。
「あの四面聖獣銀甕を見たとたん気持ちが変わってしまったの。やはり一緒に話に加わらしてもらうことにしたわ。私の分のコーヒーも造ってきちゃうのでちょっと待っててね。」
と、にこやかに、仲間入りの宣言をした。
既に午前11時を回っていたが、不思議なことに、客が誰一人来ていないのであった。窓の外を眺めていた西畑記者は、先ほどから、店の入り口に近づいてくる人はいても、店の中を覗きこんでは、首を傾げ、皆通り過ぎて行ってしまうことに気がついていた。
ママさんが、自分のコーヒーカップを右手に持ちながら、西畑記者と紅蓮が座っているテーブルに、三人が直角三角形の頂点に位置するように腰をかけた。西畑記者からは、四面聖獣銀甕が正面に見え、左手に紅蓮、右手にママさんが位置することになった。
腰をかけたママさんは、「いいから先を続けて、聞いているうちに話を呑み込んで話に加われるようにするから。」といって先を急がせた。
「では、先ほどの続きの話をさせてもらってよろしいかな?」と西畑記者が、紅蓮の顔を覗き込むようにして同意を得る言葉を発した。
つづく