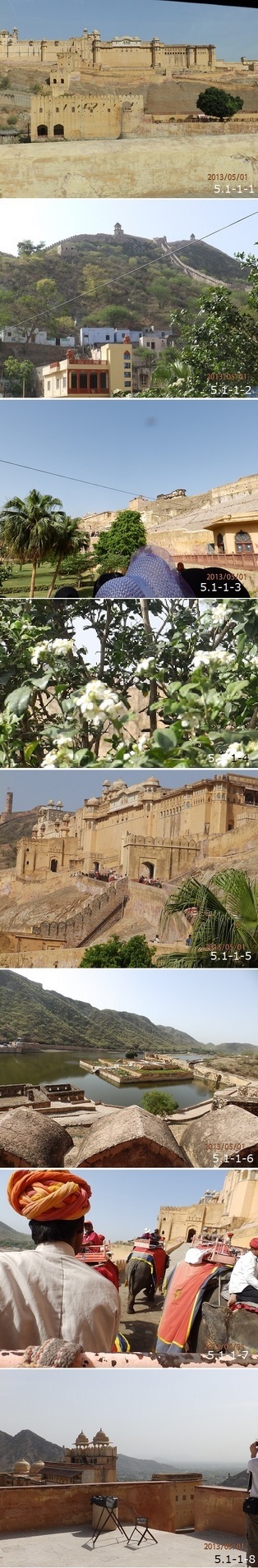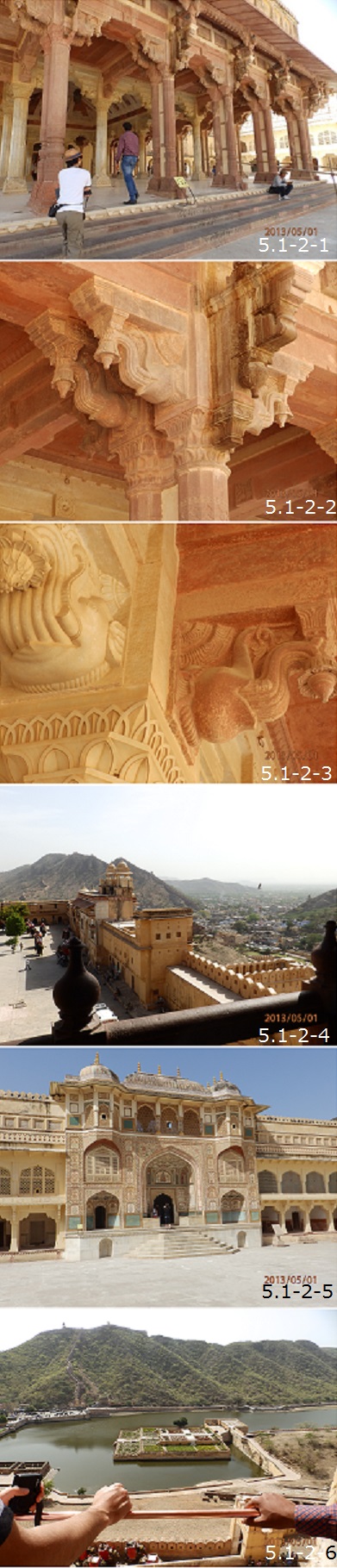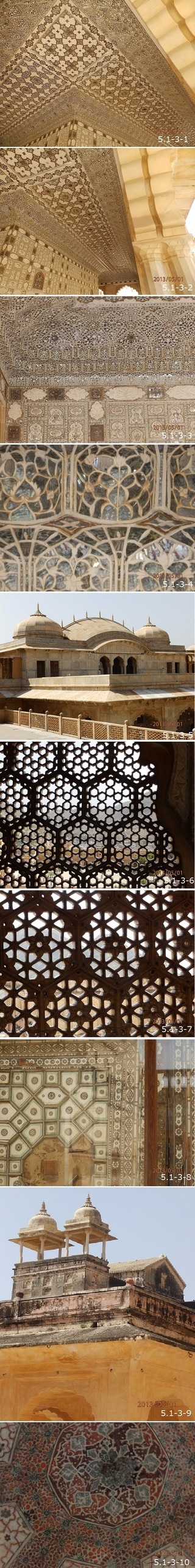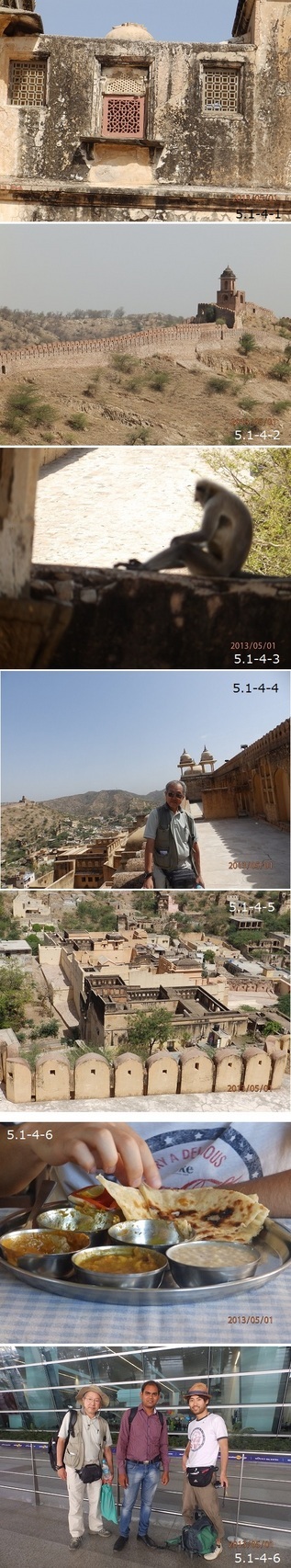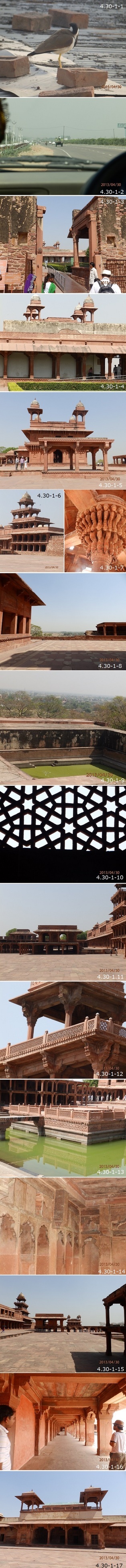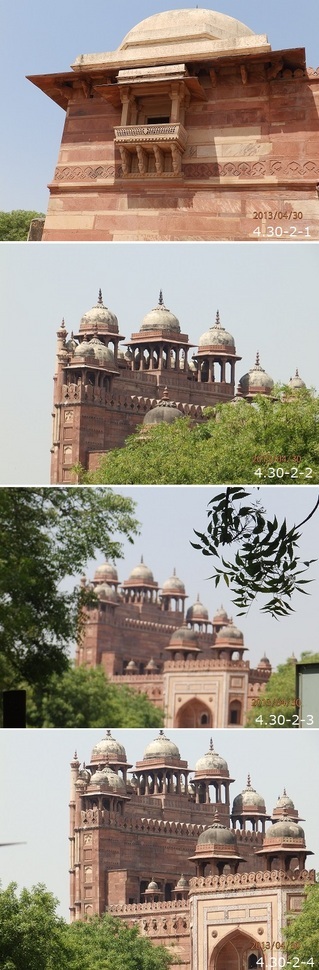| 3. ������̗�(2016.5.24�`5/29)D1�A5��24���@NH929�A�������c10:10�|�Y�B12:50�����A�Y�B��`�}��
�@�@�@�@�@���F�Y�B����V���z鲁����X
�@�@�@�@�@�Z���F�Y�B�s�����`�H21��
�@�O����̓��q�z�e�����c�ɖ�21��30���������������́A�����̑����疞�����������茩����i�ʐ^5.23-1-1�j�قǂ̍D�V�ŁA��������̍Y�B�̈��V��̓V�C�\��͐M�����Ȃ��قǂł������B���̃z�e���͍ŋ߂̑O���̒�h�ƂȂ��Ă���B�ŋߒʂ��n�߂����|��������A��A�[���A�H���O�ɁA�o�����Ă���̂ŁA�[�H�̓z�e�����̃R���r�j�ōw�������ٓ��ł������B�O���A�R���r�j�ٓ��ɂ��[�H�A�����̒��H�i���ɂ���A�َq�p��+�����j�͖��x�̃R�[�X�ƂȂ��Ă���B
�@��5/24�i�j�́A�z�e�������6�F50���̃V���g���o�X�ɏ��A���^�[�~�i���o�R�ő��^�[�~�i���������B���肵����i7������]��c�iG7�j�̊J�Ê��Ԃɂ�����̂ŁA�����̃o�X���ł̃p�X�|�[�g�`�F�b�N�́A������茵�����̂ł͂Ȃ����Ɨ\���������A�`�F�b�N���̂��̂����������B
�@���^�[�~�i��������A������邱�Ƃ́A���n�Ŏg�p�\��WiFi���[�^�̎ؗp�������B�����Ȃ�u�e���R���X�N�G�A�v�ł̎ؗp�̂��肾�������A�E�F�u���O�ؗp�o�^���ɁA�������̂��郏�C�z�[�E�l�b�g�ɐ\�����݂����Ă��܂����ׁAQL���C�i�[�Ƃ����R�[�i�[�ł̎ؗp�ƂȂ�A�Ή����Ί炪�Ȃ��A���܂芴���̗ǂ����̂ł͂Ȃ������B���Ȃ݂ɁA�ؗp��́A����ی����A���o�C���E�o�b�e���[�ؗp�����݂ŁA6���ԂŁA6,396�~�i�ō��݁j���������A�ȏ�̗��ҁi�v2,692�~:�ېőO�j�͕s�v�Ȃ̂ŁA3,264�~�i�ېőO�j�ōς܂��悩�����̂��B��������A�m�[�gPC�����Q���Ȃ����Ƃɂ���A���̋��z���s�v�ŁA�o�b�O���̃X�y�[�X���d�ʂ��y���Ȃ�A�ǂ����Ƃ���Ȃ̂��B����͂������悤�B
�@���c��10:10��NH929�ցi����18K�j�ɏ�荞�݁A��3���Ԃ̋�̗����o�čY�B��`�ɗ\��̖�30���O�ɓ��������B�@���H�͓��A�a�H�i�ʐ^5.24-1-1�j�ŁA����قǂ��܂��͂Ȃ������B���A�a�H��\�Ă���l�́A���ȃV�[�g�̔w�����ꕔ�ɖڈ�ƂȂ�V�[����\��A�z�H����q���斱���ɖڗ��悤�ɂ���B����Ǝ��͂̍��Ȃ̐l����͊�ق̖ڂł݂��邱�ƂɂȂ�B
�@�v���Ԃ�ɑ��N���������̂ŁA����������Ă���Ƃ���֍����o���ꂽ�̂ŁA�b���C�����Ȃ��A�q���斱���ɖ��f�������������m��Ȃ��B�H����Ăы���������Ă��邤���ɁA����30���O�̃A�i�E���X���������B�_�Ԃ��č��x�������Ă����Ă�̂ŁA�Y�B�͉J���A�ǂ��ē܂肾�낤���Ƃ����������B
�@��قǂ̃A�i�E���X�ŁA�\����30���قǑO�ɒ��������悤���B�����̗l�ɁA�����葱�������āA�Ō�Ɉ��S�`�F�b�N�����āA�������r�[�Ɏ���ƁA������X���[�K�C�h�߂Ă���邨������p�őh���Ί�Ŏ��U���Č}���Ă��ꂽ�B
�@���n�ł�D1���n�܂����B�J�͍~���Ă��Ȃ��B����́AD2�ŗǏ���Ղ��ό�����\��ɂȂ��Ă����̂ŁA�����ɔ�r�I�߂��A���̖k���ɂ��鏤�Ǝ{�݁g����V���h���ɂ���Y�B����V���z鲁����X��ڎw���A�p����^�]�̎��Ɨp�ԎO�H�p�W�F���Ō��������B�r�����̃p�W�F���̑��z�����p����̂���l�̒����Ζ����Ă���Y�B�s�̎s�����i�ʐ^5.24-1-2�j���������B
�@�r���A�u���܂���Ɓg��墩�H�h�v�Ƃ�����ʕW���i�ʐ^5.24-1-4�j�ɏo������B�p����A������̏Z�ރ}���V�������ʂ��Ă��铹�H�ł���B�O�X��̒������s�ł́A�[�H�̏ē��p�[�e�B�܂ł̑ҋ@���Ԃ̂ЂƎ���ނ�̃}���V�����ł��낪���Ă�������Ƃ��낾�B��墩�H�������Α��ɐ��N�H���i�X�[�p�[������A�{�̖�A�ʕ��A�N�����ǂ̗l�Ȃ��̂����w�����Ă�����Ă���B
�@�b��߂��B
�@���s���Ă��铹�H�̗����̌����ɂ͏��X�A���Ƃ��킸�A���H�ɖʂ����Ƃ���ɑ���ƂȂ�E�����X�ƂȂ����Ă���B�p����H���A�u9���ɐ�i20������]��cG20���J�×\��ŁA�o�ȃ����o�[�̈ړ��Ɏg���铹�H�ɖʂ������ׂĂ̌������̈�ĉ��ϒ����H��������B�v�̂��������B���H���̂��̂��H�����̏�������A���Ɍ����_�߂��̓��H�H���͉^�]�ҋ������ŁA�n�����p������A�r���ŁA�ԈႦ�Ă��܂����B
�@���O�ɁAD1�̏h���\��z�e���Y�B����V���z鲁����X�i�z鲁����Brook�i�u���[�N�j�j�Ƃ��̎��͂̒n�}��web�Œ��ׂ�ƁA�����T�ɓV�ڎR�ʂ肪���邱�ƂɋC�Â��A���O���p����ɁA���̗L���ȗj�ϓV�ڂ̓V�ڂƊW���肩�A�Ƃ�����������Ă���B����ɑ��ȉ��̕ԓ������[���ł�����Ă����B
�@����2.�@�uD1�h���z�e���̎��Ӓn�}�ׂĂ݂�ƁA�g�V�ڎR�ʂ�h�Ƃ����ʂ肪���邱�ƂɋC�����܂����B���́u�V�ڎR�v�́A�V���ւɊW���Ă���Ɛ������Ă��܂����A���̃z�e���̋ߖT�ɁA�q������̂ł��傤���H����ł�����ł��Ȃ����Ǝv���܂����A�\�ł��傤���H�v
�@����2�F�u�V�ڎR�͍Y�B�̐����A80�L�����ꂽ�Ƃ���ł����A�v�̎��ォ��q�ŏĂ���������Ă��āA�u�V�ڒ��q�v�ƌ������A��̓I�ȗq��Ղɂ��Ă̏ڂ��������͗L��܂���B���N�̔N�����A�V�ڎR�������Ă���Ո��s�̔����ق���������\��ł���܂��B�ٓ��ł͓V�ڗq�ɂ��Ă����Ȃǂ��W������邱�ƂɂȂ�Ǝv���܂��B�v
�@�M�҂���̎���i�lj�����j�F�u�q�ϓV�ځi�悤�ւ�Ă�����j�Ƃ����A���ɂ��H�ȓ����킪���E��4��������A���̂���3�����{�ɂ���̂������ł��B�����N���Č��ł��Ă��Ȃ����Ƃł��L���ŁA���|������Ă���l�ɂƂ��ẮA7�s�v�c�̈�Ȃ̂ł��B���N�̔N�����ɁA�V�ڎR�������Ă���Ո��s�̔����ي������A�ٓ��ɏĂ����u�V�ځv���W�������Ȃ猩�w�������ł��ˁB���N�̔N�����Ƃ����̂Ȃ�A11�A12������Ɏ���̒����ό����v�悵�����Ȃ�܂��ˁB�܂����k�����ĉ������B�v
�@���̌�A�j�ϓV�ڂ̍Č����ɂ��ẮA�u�j�ϓV�ڂ́A���̌���������������A�Č��ł���悤�ɂȂ����Ƃ����s�u�ԑg���������Ƃ�����܂��B�P�O�N���炢�O�̂��Ƃł��傤���B�v�ƁA40�N���̕t�������ŗq�Ƃɏڂ����s.�s���������Ă��ꂽ�B��×�����l�b�g�Љ�ł́A�ꂩ������݂̂ł͐M�����Ɍ�����̂ł���B
�@�ŏI�I���p����̓����F�u����A���ׂĂ��瑊�k�����ĉ������B�v
�@�ȏ�̂������v���o���A�p����ɁA�ȏ�̘b������[���ł͂Ȃ��A��b�ŏ����Ԃ��Ă݂��B����ɑ��A�p����H���A�u���A�ʍs���Ă��邱�̒ʂ肪�V�ڎR�ʂ�ł��B�v�m���ɂ��̒ʂ�A���H�W���i�ʐ^5.24-1-3�j���炻�ꂪ�m�F�ł����B
�@�����āA�r���A�u���܂���Ɓg��墩�H�h�v�Ƃ�����ʕW���i�ʐ^5.24-1-4�j�ɏo������B�p����A������̏Z�ރ}���V�������ʂ��Ă��铹�H�ł���B�O�X��̒������s�ł́A�[�H�̏ē��p�[�e�B�܂ł̑ҋ@���Ԃ̂ЂƎ���ނ�̃}���V�����ł��낪���Ă�������Ƃ��낾�B��墩�H�������Α��ɐ��N�H���i�X�[�p�[������A�{�̖�A�ʕ��A�N�����ǂ̗l�Ȃ��̂����w�����Ă�����Ă���
�@�r��G20�Ή��̓��H�H���ׁ̈A�p������^�]���ɂ����Ƃ��낪�������悤�����A�Ԃ��Ȃ��z�e���ɒ������B�z�e�����́A�g�Y�B����V���z鲁����X�h�ŁA���⎼�n�����i�ʐ^4.24-2-1�j�Ƃ����A�ό��n�Ƃ��ď����������������O���{���W���I�Ɍ��݂������Ɓi��y�j�Z���^�[�i�ʐ^5.24-2-2�j���ɂ������B
�@���̃z�e���Ɍ��n����14�F00�O��Ƀ`�F�b�N�C�������B�p�X�|�[�g���p����ɓn���ƁA�`�F�b�N�C���̎葱���i�ʐ^5.24-1-5�j�S�Ă��p������Ă����̂��B���r�[�i�ʐ^5.24-1-6�j�͋������A�������Ƃ������������̕��͋C�����B
�@30���قNjx���ƁA500�������ꂽ�Ƃ���ɂ���Ԏs������w���邱�Ƃɂ����B�p����͉ƒ�؉������Ă��āA���X���]�Ԃł����֔������ɗ���ƌ����B�u����Ԏs�v�i�ʐ^5.24-2-3�j�Ƃ����ԉʎ����|�֘A���i�ƁA���̂��������Ă���X�i�ʐ^5.24-2-6�j���W���s��i�ʐ^5.24-2-5�j�ł���A�̔����Ă���Ԏ�Ƃ��đ��������̂́A�u�[�Q���r���A�A���A�T�{�e���ށA�o���ނ��A�ʎ��ł́A�r���A�R���A�u���[�x���[�A�����S�A�u�h�[�Ȃǂ��̔�����Ă����B���ɂ̓T�{�e�����X�i�ʐ^5.24-2-7�j���������B
�@�ʎ����̈�A�̃J�^���O/�p���t���b�g��������Ă݂Ă��邤���ɁA���{�Ō����u���z�ԁv�͒����ł́u�T���i�V���E�L���E�j�v�Ƃ������Ƃ����������B�������̂��قȂ錾�t�ŕ\������̂͌���̈قȂ鍑���u�ł͕��ʂ̂��Ƃł��邪�A�������t���قȂ���̂�\���ꍇ�A����������₷���B���ɓ����������g�������u�̏ꍇ�ɍ�������B
�@�Ⴆ�g�莆�h�Ə����ƁA���{��ł̓��^�[�ł���̂ɑ��A������ł̓g�C���b�g�E�y�[�p���w���A�܂�������Łg���h�Ə������̂��A���{��ł́g�w�h�̂��Ƃł���A���Ƃ͈قȂ���ł���B�܂��A�K�ߕ����������̉����̜d��Q������A�u����͎��̈��l�v�Ɠ��{�l�ɏЉ����ǂ��Ȃ邩�A�g�ȁh�Ƃ����Ӗ��́g���l�h���A���{�ł͕s�ς̑���A�Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂��A�u���l���Č����̏�Ɍ����Ƃ͂Ȃ�Ǝ���ȁB�v�A�ƂȂ�A�O����ɔ��W���鋰�ꂪ�o�Ă���B�d��Q�����e�A�����ł��邾���ɁA�܂Ƃ��Ɉ��l�Ǝ���Ă��܂����{�l�����邩���m��Ȃ��B
�@�����l���A�u����͔��ł���B�v�Ƃ����̂ɑ��A���{�l���u����A�����ł͂Ȃ��w�ł���B�v�Ƃ����o���̂���Ⴂ���N�����ꍇ�A�����ł͐_���Ƃ��āA���Ђ⒘���l�̕���ɐA�����邱�Ƃ̑����_���Ȕ��i���{��ł͞w�j�Ȃ̂ŁA�����ے肳�ꂽ��ǂ��C���ł͂����Ȃ��ł��낤�B�����Ԃ̐����I�X���Ⴂ�̌����ɁA���̂悤�ȁA���t�̃X���Ⴂ��������Ηǂ����B
�@���āA�Ԏs�����ɂ��āA�z�e���̂��鐼��V���֖߂邱�Ƃɂ����B�����H�͒n�����i�ʐ^5.24-3-1�j�œn��B�U��Ԃ��Ă݂�ƁA������100�����Ȃ������ȎR�i�ʐ^5.24-3-2�j���������B�p����ɁB�u�A�����ČÕ��ł����H�v�ƕ��������B�u�Y�B�ɂ́A���̂悤�ȁA�������R����R����B�v�Ƃ̕Ԏ��������B
�@�����āA���⎼�n�֑����Ă���Ǝv�����i�ʐ^5.24-3-3�j��n���O�̓��֍��܂��A�U���H��i�ށA�r���A���̋G�߁i�~�J�j�ɂ́A���{�ł��悭���ڂɂ����鉩�F�������~�̉ԁi�ʐ^5.24-3-4�j�����ĐS���Ȃ��܂����B�����~�͎��z�ԓ��l�A�~�J�ɉf����Ԃƒm���钆�������Y�n�̉Ԃł���B�܂��}����ł̎��i5.24-3-5�j�ɂ��������A�{�[�g���y���ސl�i�ʐ^5.24-3-6�j�A�ނ���y���ސl�i�ʐ^5.24-3-7�j�ȂǗl�X�ł���B
�@�E�܂���Əo�����n��B�������猩����i�ʐ^5.24-3-8�j�́A�܂��Ɏ��n�s�����v�킹��B����n��I���ƁA�u���⍑�Ǝ��n�����v�E�u�������n�����فv�Ə����ꂽ�ē��i�ʐ^5.24-4-1�j�����ꂽ�B�����炭�A���������ƌ�y�Z���^�[����������┎���قւ̓�����Ȃ̂ł��낤�B���̖T�ɁA�u�Y�B���⍑�Ǝ��n�����S�i�}�v�Ə����ꂽ�ē��i�ʐ^5.24-4-2�j������A�悭����ƁA������̑��A�p��A���{��A�n���O����̐����������������B���ꂩ�瑽���̊C�O�ό��q���Ăэ������Ƃ̎Z�i�ł��낤�B
�@���������́A�t�ɏ��ƌ�y�Z���^�[���ցA�����Ă䂭���ƂɂȂ�B���̏؋��ɉ��O�i���R�[�i�[�i�ʐ^5.24-4-3�j������A�X�ɐi�ނƖk���N���X�g�����i�ʐ^5.24-4-4�j��A�������̔�����g��q�h�Ƃ������̓X�܁i�ʐ^5.24-4-5�j�����ꂽ�B������͐��i�ʐ^5.24-4-6�j�����C���������B�I�ɒĂ���̂͐��������̉z�B���i�ʐ^5.24-4-5�j�A�e�[�u���ɒ�Ă���͉̂��ΐF�������̗�����i�ʐ^5.24-4-6�j�~�����Ǝv�������A����ł́A�͂邩�Ɉ����ɓ����̂��̂���ɓ���ɈႢ�Ȃ��Ɨ\�z���A�w���͂�߂��B�����̓X���ɁA�u�i�����́j�k���N�l���H�v�ƕ����ꂽ�炵���B
�@�����čX�ɕ����ƁA�˗ނ��������X�g�������������̂ŁA�����ŗ[�H��ۂ邱�Ƃɂ����B
�q�͖w�Nj����A�X���O�̕��͋C�ł������B����̒������s�O�����̖ڋʂɂ��Ă���_吞�ƁA�����܂��ӂ肩�����ăp�����Z�b�g�i�ʐ^5.24-4-7�j�Œ������A�H�ׂ��B�����āA�����̏o��������8�F10�Ɩ��A�����̓z�e���ɁA�p����͎���ɖ߂����B
�@���A�������炵�����A���ƌ�y�{�݂����ɁA�n���f��يX�A�t�B�b�g�l�X�E�N���u�Ȃnj�y�{�݂��ʘH���猩�w�������A�ݔ��͏[�����Ă��āA�x���ɂ͍Y�B�s���ő���킢���邱�Ƃ��e�Ղɑz���ł����B
�@�@�@�@�@�{�e�@���@�@��
|