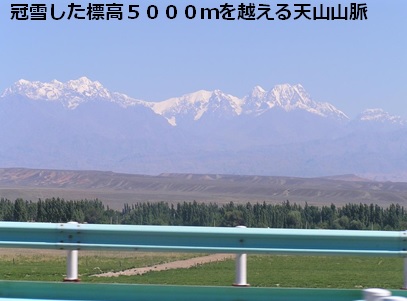�`���i���{�j�ւ̕����`���̓���(�ŏI��j�����i����1�Ɠ����j�@�u�����`���̓����v�������������J�Ȍ�����������ƁA�u���{�֕������`�d����܂ł̓��v�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
�@�����@���Ƃ��������́A��g�ŏI���̂ł͂Ȃ��A�r���̓`���o�H���e���ꂽ�n��ɂ����ĐV���ȉ��߂������A�n��ɂ���ẮA���̐V�������߂̕����蒅����A�Ƃ��������������Ă���ꍇ�������A���g�̓`�d�ȏ�ɉe�����傫���Ȃ�悤�Ɏv���܂��B
�@
�@���������Ӗ��ł́A�ŏ��ɓ��{�ɓ`�d���������ȏ�ɁA��ɓ`�����Ă������`�̕���������Ղ���e���₷�������̐l�Ɏx������邱�ƂɂȂ�̂��Ǝv���Ă��܂��B
�@�܂��A����n��ŐM�Ƃ�����������e�����̂́A���̒n��Ɏ�e����镗�y����������Ă��邩��ł���A���̏����ɈӐ}�����Ɉ���Ă��ꂽ�l�������݂����\��������A���̎���́A�������`�Ƃ���鎞�_�ɔ�ׁA�ƂĂ��Ȃ��̂����m��܂���B
�@�����l����ƁA�V�������߂������㐢�����ł͂Ȃ��B�����啝�ɑk���ĕ�������e����镗�y�����������N�_�ƂȂ�o�����ɂ��ڂ�������K�v������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�@�]���āA���������߂ē��{�ɓ`�������ƌ����Ă���N��݂̂�����̂ł͂Ȃ��A����ȑO�ɂ����j�̕\�Ɍ���Ă��Ȃ��l�B�ɂ��`�d�A�����Ă���܂ł̌��`�Ƃ͈Ⴄ�`�d�o�H��S����B�ɂ��`�d���������\��������A����𑍍��I�Ɍ��Ȃ��Ɛ^�̕����`���Ƃ͌����Ȃ��l�Ɏv���̂ł��B�����͈ȉ���4�̏����ɏW���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
1.���`�������̐l�ɂ���Ďx������邱�ƁB
2.�`�d�o�H�͗��H�A�C�H���邢�͗��҂̃n�C�u���b�h�B�ꍇ�ɂ���Ă͊C�H�Ɠ������H�ł���^�͂��`�d�o�H�̈ꕔ��S�����Ƃ����낤�B�C���h�Ɠ��{�Ƃ̊Ԃɂ͗l�X�ȘA���H������܂��B
3.�`�d�̒S����i�ꍇ�ɂ���Ă͔��Q�ɂ���ē`����j�~���镉�̒S����j�����āA�V�V�n�����߁A�J�_�������ȒS���l���������ƁB
4.�`�d��ɂ��Ƃ��Ƃ������M�Ƃ̋����A�Z���Ƃ��������ݍ�p�̖��ɐ^�̕����`�����������B
�@�ƍl�����܂��B�����̗v�f���C���h�˂̒n�Ƃ��āA���{�ɓ`�d����܂łɁA��L1�`4���ǂ̗l�ɍ�p���Ă������A���肵�����������Ƃɂ܂Ƃ߂Ă݂����Ǝv���Ă���̂ł��B
�@���肵�������Ƃ́A������������C���h�A�X�ɂ͍����̓ޗǁA���s���̕����֘A���@��_�Ђ�q�ς��A���������ƂŁA�����ɂ��āA�u���O�ɋL�ڂ������͂��甲���]�L������A�ڍ��ɂ��ẮAWikipedia ���Q�l�ɂ����Ă����������肵�܂����B
�ȉ��ɑ區�ڂ��A�@�@ ���ڔԍ��@���ڃ^�C�g��(18pts)�A�Ł@
�區�ړ��ɒ����ڂ��@�@�����ڔԍ��@�����ڃ^�C�g��(16pts)�A�Ł@
�X�ɒ����ړ��ɏ����ڂ��y�����ڔԍ��@�����ڃ^�C�g���z�i14pts�j�ŕ\���܂����B
�@
�O��܂ł̑���`��\��́A�ȉ��̍��ڂɂ��āA�M�҂̎v���������Ƃɂ��ďЉ���Ă��������܂����B
����F1)�������˂̒n�C���h�ł̎߉ށA���牤(�����傩����)�A�J�j�V�J���ƃq���Y�[��
2�j�ŏ��̓`���n�����A�W�A�̃K���_�[���A�匎���i�����������j
3�j�������c�_�A�w���j���i�ӂƂ��傤�j�x���`�A�n�c��⑾���]�̃��[�c�͛I��
4�j�匎���̌��A�|���N�̌��A�]�����@�����č�������̎q���A
5�j�V���N���[�h�i�J�V���K���A�T�(����)���A����(�������傤)���A�g���t�@���A����(�Ƃ�)
6�j�_���(����Ȃ傤)�̐M�@���](���傤����)�`�d�o�H
7�j�i�n��(����)�ɂ�鐼�W(��������)�����B�i�n��Ǝהn�䍑(��܂�������)
8�j�k���O���u�ɓo�ꂵ�������̔z���Ί�ɂ��āA�����Ĕ��n��
9�j�k���ƍY�B�����ԋ��R��^��
����F10�j�������˂̒n�C���h�A�@�߉�(���Ⴉ)�A�A�A�V���J���A�B�J�j�V�J���A�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@11�j�������Y(���܂炶�イ)�A���}��(�ԂƂ��傤)�A���̒�q����(�ǂ�����)�A�@��(�ق�����)�A����(���傤)
12�j �Ӑ^(����)
13) �������Q�E�e��
14) �����A�V���A�S�ςւ̕����`��
15) �������̉����A�����Z�p�͕S�ρA�o����͍����
16) �O�`��䘌�
17) �����쒩�A���W�A��v�A���A��(����)
18) ���̍c��(�����Ă�)��F(�ڂ���)�A����A���ʉ��ł̘`���Ƃ̐ڐG
19)�@�����E�S�ρE�V���݂͌��ɘA�g�E�R���̂���Ԃ��A�S�ς�538�N�J�s�ȂǑ�ςȎ���
20)�@�`���i���{�j�ւ̕����`��
�@�@�y�Q�l.538�N�i��߁j���i�ȉ�Wikipedia���j�z
�@ �����`���A���`�A���I�ȐM�Ƃ��Ă̓`���z
�y���牤�R�Γ����z
��O��F22�j�ܑ�R
23�j�O�����猩���`��
24) ���̑����A�����`���A�n�c�鎀��̕��a��
25�j�|���N�A���q�g��
26) �����̐ΌA���@
�@�j�����@�����A
�A�j�_���ΌA���@
�B�j�ΌA�ɐ��ތ���Ő�l
�C�j�_���ΌA���@��O�A�̑���
�D�j�����Z�a�̗��j
�E�j�ΌA���@�̑��A���@�@
�F�j�c��ꑰ�̑����̗��j
�G�j�،��O���ɂ���
�H�j�����̓`�d�o�H�i���}���Ɠ����j
��l��F27) ���z�̒n�j�Ɨ��j�A�㒩�Ós
�@) ���z ���n��
�A�j����ΌA���@
28�j�����R�ΌA���@�@
29�j�g���t�@��
�@)�g���t�@���E�����̏�
�A)�g���t�@���E�A�X�^�[�i��Q
�B)�g���t�@���E�[�x�N���N�畧�� �@�}�j��
�C)�g���t�@���E�Ή��R�@
��܉�F30�j�呫�����@�i�����̐��E�ρj
�@�j�����Ō���“�O�E”�Ƃ�
�A�j�u�Z���։�v�̐��E�Ƃ�
�y�Z��B�S�z
�y�\������z
�B�j�k�R��
�C�j���̘Ȃ܂��A�����̋����@
31�j��X�̐M�ƕ����̓`�d���[�g�i�`���[�g�}�j
�y����1�z
�y����2�z
�y����3�z
�y����4�z
32)�قȂ�M�i�@���j�Ԃ̏K��
�@�j�}�j���i��7�j
�A�j�q���Y�[���ƕ����̊ւ�i��0�j
�B�j���]�i�_��j����
�C�j���ɗ��M��
�y�̓�(���傤�Ƃ�)�V�c�ɂ��_��i�_(����������)4�N�i770�j�̕S��
�@���ɗ�������(�ЂႭ�܂�Ƃ�����ɂ�����イ�����傤)�G�s�\�[�h�z
�y���ߍ]�s�Γ����G�s�\�[�h�z
�y����6�N�i1003�j����G�s�\�[�h�z
�y�d���A���牤���ɗ��a�Č��̍ޖG�s�\�[�h�z
�y�_������(������ɂ傤��)�A�������`���G�s�\�[�h�z
�y���d��/�������G�s�\�[�h�z
�y�������牤���s�G�s�\�[�h�z
�y���牤���̓��{�̎��@�Ƒ傫���قȂ�_�F�����Ɛ����̑Ώ̐��A�ۘO(����
��)�Ə��O(���傤�낤)�̕��݁z
��Z��F33)�`���i���{�j�̐M�i���S���̐_�A�_���j�ɑ傫�ȉe�����y�ڂ����M��
�@�j���_�����@�������c�_
�A�j�匎��-�|���N-�I��-�����U�E�����]-�����E��-�`�l���u���̑����̎q���v-�_���V�c
�B�j�I��(���傤����)��㳑�(���傤����)�A㳑�(�����)
�C�j����1
�y��������������ϗ��z�@
�yD4-1:�E�����`�F�V�r1 (������1)�z
�yD4-2:�E�����`�F�V�r2 (������2)�z
�yD4-3:�E�����`�F�V�r3 (������3)�z
�yD4-4:�E�����`�F�V�r4 (������4) �z
�yD4-5:�E�����`�E�V�r5�i�E�B�O���l�A�p�I�j�z
�yD4-6:�E�����`�E�V�r6(�{�S�^��)�z
�D�j�@
�E�j����2
�F) �A�����̘`���i���{�j�ւ̓`�d
�y���� - ��������z
�y�k�R�_�Ёz
�y�V�q�V�c�z
�y�V���V�c�z
�y�Ė��V�c�z
�掵��:34�j���������j�ɖ����c���͂������A�O���u����Ɍ��Ŗ����c����笮�Z
35�j�`���i���{�j�ւ̕����`���̉ߒ��ŁA����ꂽ���K�A�V���ɉ���������K
�@�j.�q��̎d��
�y��敧���Ƃ́z
�y����i������j�����Ƃ́z
�A)�����̂ǂ��ɋ��Ă����̗̂l�ȐS�n�悢���̂���������
�y�_��ȑ嗝 �����O�����i1�`4�j�z
�B) �����ΌA���@
�y�����@�_��̗��@�����i18�j“�o����” �z
�C).�_���K��
�y���t�̖� �ޗǁ@������i�Ƃ��݂̂ˁj�k�R�i����j�_�Ё@***�@�k���̂͂��܂�@***]�z�ySAIKAI2010�@�����_�Ёz
�D)���ӕ�F�M�Ƒ̌`�E�p��
�y�㐶�M�@�\�������z
�y�����M�� �z
�y���ӕ�F�M�z
[���ӕ�F�̌o�T]
[���ӕ�F���̎p��]
[���ӕ�F���̗R��]
[���ӕ�F���̐���]
�攪��:36�j���{�n����̕����̕ϑJ�ƁA�S�����l���i����1�j
�@�j.�������q
�A�j�Ǖ�
[�H�@�����i���u�j�i2�j�z
�B�j��C
�y�͛G�n��ՂƁA�M�B�Ȃ̎��R�Ə��������ɐG�ꍇ�����z
�y���z���O���u�_�B���O���v�z
�y���t�̖� �ޗǁ@���̋��@�����@***�@�Ӑ^�̎��O�@***�z
�y��C���K�ꂽ�J�告�����A�i9/25�j�z
�y���������܌Ós���䂭�@5.�����ŌÂ̕������A���n���i9/22�j�z
�y���s�@�~�̗��i����2�F�\���`1�`�j�z
�y�������_�i34�j�@<<<�@35.�@���o�E���P���F�@>>>�z
�y �������_�i29�j�@<<<�@30. �����֎��@>>>�z
�C�j�Ő�
�y�����Ɩ����z
�D�j�e�a���l
�y���o�Ɓz
�y�@�R��l�Ƃ̏o��B��̍K���Ɂz
�y�j�V�r�̂������z
�y�e���ɂ�藬�Y�z
�y�֓��ł�20�N�ԁz
�y����ɗ�܂��z
�E�j����l�i903�N - 972�N�j
�y���s�@�~�̗��i����2�F�\���`2�`�j�z�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�y�����z
����F37�j���{�ւ̕����`����̎���I�ϑJ�ƁA�S�����l���i2�j
�@�j���{�n����̕����̎���I�ϑJ�B��y�v�z
�A�j���{�̊e����ɂ������y�M��
�y����E�ޗǎ���z
�y��������z
�y�������㏉���z
�y�z�~�m�y�z
�y�z�nj��y�z
�y�������㒆���z
�y�z���y�z
�y�z���M�y�z
�y�z�c���ۈ��y�z
�y�������㖖���z
�y�z�u���@�v�̓����y�z
�y�z�ǔE�y�z
�y���q����z
�y�z�@�R�i����j�y�z
�y�z�e�a�y�z
�y�z��Ձy�z
��\��F 38�j���@�v�z�@�ɂ�閯�O�̓��h��}�����y�v�z
�@�j���@�v�z�Ƃ�
�A�j��y�v�z
�B�j����̐��E�A�Ɋy��y�A��y�M�A���@�v�z
�C�j���{�̊e����ɂ������y�M��
�y����E�ޗǎ���z
�y��������z
�y�������㏉���z
�y�~�m�F�V���y���̔��ˁz
�y�nj��F��b�R����̒����̑c�z
�y�������㒆���z
�y���F�x�O���̑n�n�z
�y���M�F��y���̑c�z
�y�c���ۈ��F�w���{�����Ɋy�L�x�A��O�����ւ̓]���z
�y�������㖖���z
�y�z�u���@�v�̓����y�z
�y�ǔE�F�Z�ʔO���z
�y���q����z
�y�@�R�i����j�F�u��C�O���v��y�@�z
�y�e�a�F�w���s�M�x�A��y�^�@�z
�y��ՁF���@�̊J�c�A�x�O���z
��������
�ŏI���ł����A�`���i���{�j�̂��Ƃ����グ�������̌Îj���ɂ��ă��r���[�������Ǝv���܂��B
39) �`���i���{�j�����グ�Ă���C�O�̎j��
�@�j �T�v�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�A�j�w�_�t�x
�B�j�w�R�C�o�x
�C�j�w�����x
�D�j�w�㊿���x
�y�w�k�j�x�`���`�z
�y�w�@���x�`���`�z
�y�w�������x�`���E���{���`�z
�y�z�`���嗐�ɂ��āy�z
�y�w�O���u�x鰏� ��30 ���Γ` �`�l�i鰎u�`�l�`�j�z
�y�w�㊿���x��85�@���Η�B��75�z
�y�w�����x��54 ��B��48 ���ΙB ���Ώ� �`�z
�y�w�@���x��81 ��B��46 ���ΙB 俀���z
�y�w�k�j�x��94 ��B��82 �`���z
�E�j�w鰎u�x�`�l�`�x�w�O���u�x鰏����O�\�@�G�ۑN�ړ��Γ`�@�`�l���i������w鰎u�`�l�`�x�j
�F�j�w�W���x
�G�j�w�v���x
�H�j�w���x
�I�j�w���E�v�}�x
�y�z�I.1�`���ɂ��Ă̋L�q�y�z
�y�z�I.2�z�����i�V���j�ɂ��Ă̋L�q�y�z
ⅺ�j�w�����x
ⅻ�j�w���x
�I�B�j�w�k�j�x
�y�I�B.1�w�k�j�x�`���`�z
�I�C�j�w��j�x
�I�D�j�w�@���x
�y�I�D.1�w�@���x���ΙB�z
�y�I�D.2�w�@���x�^�C���`�z
�I�E�j�w�������x
�I�F�j�w�V�����x
39�j�`���i���{�j�����グ�Ă���C�O�̎j���ȉ������`���Ƃ͒��ڊW����܂��A�C�O�A���ɒ����͎��X�̗��j�ɂ����Ę`���i���{�j���ǂ̗l�ȍ��Ƃ݂Ă������ɂ��āAWikipedia���甲���]�L���ďЉ�����Ǝv���܂��B�`������{�ƌĂѕ���ς����j��������܂��B
�@�j�T�v�`�̕����̏��o�́A���j�͌㊿�����ɏ����ꂽ�w�����x�n���u�i�njŁj�ł���A���j�ȊO�ł́w�_�t�x�i���[�j������B�w�����x�ł́A�`�͒��N�����̓�̊C�̒��ɂ���Ə����Ă���A�w�_�t�x�ł́A�z��Ƙ`�����L����A�`�͒����̓�̌��z�n���i�g�q�]�̉�����̓�t�߁j�Ɗ֘A������Ɛ��肵�Ă���悤�ł���B.�w�W���x��w�����x�Ȃǂł́u�����V��v�ƋL���A�`�l�����̑c�ł��鑾���̎q���Ǝ��̂��Ă������Ƃ��L�^���Ă���B
�A�j�w�_�t�x�����㊿����̉��[�i27�N - 1���I�����j���������S30��85�сi����1�т͕і��݂̂ŎU�Áj���琬��v�z���A�]�_���B���؎�`�̗��ꂩ�牤�[�͎��R��`�_�A�V�_�A�l�Ԙ_�A���j�ςȂǑ��l�Ȏ���������A����Ŕ��I�Ȑ�N�A�A�z�܍s�v�z�A�Јِ�����M�_�Ƃ��ēO��I�ɔᔻ�����B�@�ȉ��`���Ɋւ���L�ڂɂ����ă��r���[�������Ǝv���܂��B
�w����͓��{�̓ꕶ����ӊ�����퐶����O���ɂ�����A���̐����݈̍ʂ͑O1042�N�`�O1021�N�Ƃ���邪�A�w�_�t�x���̂͂��Ȃ��̑O���̎����1���I �ɏ����ꂽ���̂ł���B��賂͐H�p�A����(����)�͕��p�ƋL����Ă���̂ŁA����ɂ͒����͘`�ł����̂�Ȃ��A���ɐZ���Ƃ���Ă����Ɛ��肳���B�Ȃ��A�����ɂ́A��ŁA�E�R���A���ԑ��A���̐�������B�x
�B�j�w�R�C�o�x�����̒n�����B�����Ñ�̐퍑���ォ��`���E����i�O4���I - 3���I���j�ɂ����ď��X�ɕt�����M����Đ����������̂ƍl�����Ă���A�ŌÂ̒n�����i�n���j�Ƃ����B
�w�`�͉��ɒ��v���Ă����ƍl�����Ă������Ƃ��킩��B�������A�����͓`���W�܂��͐_�b�W�̑̍ق��Ƃ��Ă���A�u�ˋ�̍��v��u�ˋ�̎Y���v�������A�j���𒉎��ɔ��f�������̂Ƃ݂Ȃ����Ƃɂ��Ă͋^�⎋����Ă���B
�w�R�C�o�x��� �C�O���S�ł́A�����̊C���Ɂu�������v������A���̖k�Ɂu�}�K�v�������鑾�z�����鍑������Ƃ���Ă����B���̍������Ƙ`���֘A�t�����Ă���L�ڂƂ��āA�ȉ��̂��̂�����B
�Q�l�@�}�K�F�Â��́w�R�C�o�x�Ɍ�����悤�ɁA�͂邩���C��ɗ��`����̋��ł���A�������瑾�z������Ƃ���Ă����B���z��V�n�ɂ܂�鋐�Ƃ��Ă͎�⌚�Ȃǂ����ɋL�q�Ƃ��Ďc����Ă���B�Ñ�A���m�̐l�X�́A�s�V�s���̐�l�����ނƂ������[�g�s�A�u�勫���H萊�R�E���ĎR�v�ɂ�������A�����ɁA���z��������X�����Đ����Ă���Ƃ��������̎��u�}�K���v�ɂ��₩�낤�Ƃ����B
�u�H���R�v�Ɓu�}�K���v�́A�Ñ�̐_��v�z�����ł������z�ł���B�C���̂��Ȃ��ɂ́A�T�̔w�ɏ�����u��^�̖H���R�v�����ԁB�C���̒J�Ԃɂ́A���z������u����ȕ}�K���v�����т���B�Ñ�̐l�X�́u�H���R�ɐ��ސ�l�̂悤�ɒ��������A�}�K���ɏ��鑾�z�̂悤�Ɏ�Ԃ肽���v�Ƌ����肢�A�H���R�ƕ}�K���ւ̓��ۂ��̂点�Ă����Ƃ����B
�C�j�w�����x�����㊿�̏͒�̎��ɔnjŁE�Ǐ���ɂ���ĕҎ[���ꂽ�O���̂��Ƃ��L�������j���B��\�l�j�̈�B�u�{�I�v12���E�u��`�v70���E�u�\�v8���E�u�u�v10���̌v100�����琬��I�`�̂ŁA�O���̐������牤�͐����܂łɂ��ď����ꂽ�B�w�㊿���x�Ƃ̑Δ䂩��O�����Ƃ������B�w�j�L�x���ʎj�ł���̂ɑ��āA�����͏��߂Ēf��j�i��̉����ɋ���Ă̗��j���j�̌`�����Ƃ������j���ł���B�w�����x�̌`���́A��̐��j�Ҏ[�̋K�͂ƂȂ����B
�w�������j�Ř`�l�̕����̏��o�́w�����x�n���u�ł���B�`�l�ɂ��ėL�̕����ŋL�����̂́w�����x�����ɂ��ėB��ł���A���̌�̑S�Ă̐��j�ł́u�݁v�̕������p������̂ŁA�L�̕����́u�����v�̈Ӗ��ŗp�����A�u�݁v�̕����͏��݂̈Ӗ��ŗp����ꂽ���Ƃ����������B�x
�y�n���u���n���z���͐������_���ł���A���̎O���i���^�E��E�kཁj�ƈقȂ�B���̂��߁A�E�q�́A�����̒����ł͐������������s���Ă��Ȃ����Ƃ��c�O�Ɏv���A�i���Łj�C��n���ċ�ɍs�������Ɩ]�B����͗��ɂ��Ȃ��Ă���I�@�y�Q�S�̐�̊C�̒��ɘ`�l������B�S�]���ɂ킩��Ă���A ����I�ɑ��蕨�������Ă���ė��鍑���������A�ƌ����Ă���B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�y�n���u���n���z���m�C�O�L��鯷�l�@��ਓ�\�P���@�ȍΎ����ٌ��]�@��m�̊C�̊O�ɓ�鯷�l�L��B�����ē�\�]�����ׂ��A�Ύ������ė�����Č������Ɖ]�ӁB��m�̊C�̊O�ɓ�鯷�l�L��B��\���J���ɂ킩��Ă���A����I�ɑ��蕨�������Ă���ė��鍑���������A�ƌ����Ă���B
�D�j�w�㊿���x�w�㊿���x���Η�`�̒��ɘ`�i��̓��{�j�ɂ��ċL�q������A�Ñ���{�̎j���ɂȂ��Ă���B���́u�`���v�i������u�㊿���`�`�v�j�́A280�N�㐬���Ƃ����w�O���u�x�́u鰏��v���Γ`�`�l���i������u鰎u�`�l�`�v�j����ɂ����L�q�Ƃ���Ă���B
�u鰎u�`�l�`�v�ɂȂ��L�q�Ƃ��āA����������N �`�z����v���� �g�l���i��v �`���V�ɓ�E�� �������Ȉ���@�Ƃ���A����������N�i57�N�j�ɘ`�z�������v�����Ƃ���Ă���B���̂Ƃ������邪�^��������i���ϓz������j���������̎u��ŏo�y���Ă���B�܂��A����i�����N �`���������� �������S�Z�\�l�@�Ƃ�����A�i�����N�i107�N�j�ɘ`�������� ���l�ށi�J���҂��j��S�Z�\�l���サ���Ƃ���Ă���B���ꂪ�j���ɏo�Ă��閼�O�������鏉�߂Ă̘`�l�ƌ������ƂɂȂ邪�A�ꕶ�݂̂ł���A�ڂ������Ƃ͕������Ă��Ȃ��B�܂��u鰎u�`�l�`�v�ɔN��̎w�肪�Ȃ��`���嗐�i鰎u�́u�`�����v�Ƃ���j�ɂ��Ă�����E���̊ԁi147�N - 189�N�j�ƁA��܂��ł͂��邪�N��̎w�肪����B
�y�w�k�j�x�`���`�z����̎��i106�|125�N�j�A�܂����g�����v�����A�����`�z����.�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�y�w�@���x�`���`�z����̎��i106�|125�N�j�܂����g�����v�A������u�`�z���v�Ƃ����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�y�w�������x�`���E���{���`�z�`���Ƃ́A�Ấu�`�z���v�Ȃ�
���̌�͘`���嗐�Ɣږ�Ă̋L��������A�w�O���u�x�́w鰏��x���Γ`�̘`�l���i鰎u�`�l�`�j�Ɏ��Ă��邪�A�嗐�̎������u����ԁv�i����Ɨ��̎���j�Ƌ�̓I�ɋL���ȂǑ���_������B���Γ`�ɂ͂��̑��A�w�����x�n���u������p�����ƌ�����u��鯷�l�v�̋L���A�w�O���u�x�́w�����x�����`������p�����ƌ�����ΏF�Ƙ��F�i�u澶�F�v�ƌ�L�j�̋L��������B
�y�z�`���嗐�ɂ��āy�z�@�@�����̐��j�A�w�㊿���x�u���Γ`�v�A�w�O���u�x�i鰎u�`�l�`�j�A�w�����x���u���Ώ��^�v�`�ȂǂɁA�`�嗐
�i�w�㊿���x�u���Γ`�v�j�܂��͘`�����i�w�O���u�x�i鰎u�`�l�`�j�A�w�����x���u���Ώ��^�v�`�j�Ƃ��āA�T�v���̒ʂ�L�q����Ă���B�@
�@�@�@
�w�`���͂��Ƃ��ƒj�q�����Ƃ��Ă����i57�N�Ɍ㊿�̓s���z�Ɍ��g���Ċ��ϓz�������ꂽ�ϓz�����A107�N�Ɍ㊿�Ɍ��g�����`�ʓy�����������j�B70〜80�N���o�āA�`�����ő嗐�i�����̍��𑈂������j�����������B�����͗�N�i�������j�ŗ�N�Ƃ͕��ς���8�N±���N�j�������B�הn�㍑���������A�הn�㍑�̈ꏗ�q�����Ƃ��邱�Ƃō������������B����ږ�ĂƂ����B
�x
�y�w�O���u�x鰏� ��30 ���Γ` �`�l�i鰎u�`�l�`�j�z�w���̍����܂����X�j�q�����Ƃ���70〜80�N���o�Ă����B�`�����i�`�����̍��𑈂������B���ʑ��D�͗ǂ��L�鎖�����A�O���j�����킴�킴�L���͍̂����̍��Ɍ�ւ��������ꍇ�̂݁j�B8�N±���N�Ԃ����݂ɍU�ߍ������B�����ŁA��l�̏��q���������ĉ��ɂ����B���͔ږ�ĂƂ����B�S(�_)����p���Ă悭�O��f�킵���B�N���35���߂��i�����j���ł�35�ɒB����ƔN����ƕ\�������j�A�v�͖��������B�x�Ƃ���B�܂��A
�y�w�㊿���x��85�@���Η�B��75�z����E���̎����̊ԁi146�N - 189�N�j�A�`���嗐�i�`�����̍��𑈂������B�O���j�����킴�킴�L���͍̂����̍��Ɍ�ւ��������ꍇ�̂݁j�A����Ɍ݂��ɍU�ߍ����A8�N±���N���喳����ԂƂȂ����B�ږ�ĂƂ������̈�l�̏��q���L��A�N�������ł��ł��Ȃ������B�S�_����p���Ă悭�O��d�����f�킵���B�����ɉ����ċ������A���ɂ����B
�y�w�����x��54 ��B��48 ���ΙB ���Ώ� �`�z(��)���̗��̌��a�N�ԁi178〜184�j�A�`�����i�`�����̍��𑈂������B�O���j�����킴�킴�L���͍̂����̍��Ɍ�ւ��������ꍇ�̂݁j�A8�N±���N�����݂ɍU�ߍ������B�����ŁA��l�̏��q�ږ�Ă��������ĉ��ɂ����B�x�@�ȉ���2���j�̋L�q�͏�L3���̈����ʂ��ł���B
�y�w�@���x��81 ��B��46 ���ΙB 俀���z
�y�w�k�j�x��94 ��B��82 �`���z�E�j�w鰎u�x�`�l�`�x�w�O���u�x鰏����O�\�@�G�ۑN�ړ��Γ`�@�`�l���i������w鰎u�`�l�`�x�j�@�����̗��j���w�O���u�x���́u鰏��v��30���G�ۑN�ژ`�l���̗��́B���Γ`�ɂ́A�v�]�E�����E�������E挹�K�E濊�E�n�E�C�E�ْC�E�`�l�̋�����܂܂�Ă���B���Γ`�̋���Ƃ���̎O������\������Ă���B�`�l�`���A��ꕔ�͂��̎��ӂƂ̊W�ʒu������̍s�����̋L���A��͂��̌o�ϐ��������K���̋L���A��O���͂��̐����O����̑厖���̋L���A�ƕ����邱�Ƃ��ł���B�܂��A�`���̐����̐��Ɋւ���L�����ꕔ�ƍl����Ǝl���\���ɂł���B
���Γ`�̊ؓ`�`���ɂ��`�Ƃ����L�ڂ�����B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�͑ѕ��̓�ɍ݂�B�����͊C�������Č���ƂȂ��A��͘`�Ɛڂ���B��4�痢����B
�F�j�w�W���x����I�@���N10�N�i289�N�j���@�@���̐≓�̓��ɘ`�l���܂܂�Ă���ƌ��邱�Ƃ�����B�`�l�ɂ��Ă͓��Γ`�ƕ���I�A�`���ɂ��Ă͈���I�ɏ�����Ă���B�הn�䍑�ɂ��Ă̒��ڂ̋L�q�͖������A鰂̎���̘`�l��ږ�Ăɂ��Ă͏�����Ă���B�܂�266�N�́u�`�l�v�̒��v�͓��{���I�̐_���c�@�I�Ɂw�W�N�����x�i�������Ȃ��j������p���ꂽ�u�`�̏����v�̋L���ƔN������v����̂ŁA���̏����͑�^�ƍl�����Ă���B266�N�ɘ`�l�����āA�~�u�E���u���k�x�ɕ����A���J����x�ɍ��킹���Əq�ׂ��A�O����~���̂�������L�����Ɖ��߂������������Ă���B
�G�j�w�v���x�`���`�@�w�̂���c�\�i���ł��j�Z�i�݂����j��b�h�i�������イ�j���i��ʁj���A�R��i����j����i�����傤�j���A�J���i�˂�����j��硁i���Ƃ܁j���炸�B���͖ѐl�𐪂��邱�ƁA�\�܍��B���͏O���邱�ƘZ�\�Z���B�n��ĊC�k�炮�邱�ƁA��\�܍��B�x
�w���̏���́A��\�ɉ����A�ق��Ȃĕ����A�g���߁A�s�`�E�V���E�C�߁E�����E�`�E��ؘZ�����R���A�����叫�R�Ƃ����B�x
�H�j�w��ď��x��` ��O�\�� �� ����@�w�`���W�͓���Γ`�ɏ�����Ă���B�`���͑O���j�̋L�q��傫�����^�������̂ŁA�܂��������猩���`���̈ʒu�⏗���̑��݂Ȃǂ��L���B
479�N�̘`���̌��g���L���A�`�������g���ߓs�`�E�V���E�C�߁E�����E�`�E��ؘZ�����R�������叫�R����A�̍�������叫�R�ɏ��i�����x
�I�j�w���E�v�}�x�w���E�v�}�x�ɋL���ꂽ�c��ɑ�����Ӎ��⏭�������̐i�v�̗l�q�̒��ɁA�`���̋L�ڂ�����B
�y�z�I.1�`���ɂ��Ă̋L�q�y�z�@
�`���͓�Ă̌����i479�N〜482�N�j�ɁA��\�����B
�y�z�I.2�z�����i�V���j�ɂ��Ă̋L�q�y�z�z�����͌��͓��̒C�؏����̒��̈ꏬ���ł������B鰂̎���ł͐V���Ƃ����A���v�̎���ɂ͎z���Ƃ���������̍��ł���B����Ƃ��ɕ������A����Ƃ��͘`�ɕ������Ă������߁A�����͎g�҂�h���ł��Ȃ������Ƃ��Ă���B���ʓ�N�i521�N�j�ɁA��`���i�@�����j���A���߂āA�S�ςɐ��������v����g�߂�h�������B�z�����ɂ͌��N��Ƃ����邪����A�K���͍���i�����)�Ɨގ��������͂Ȃ�������Ŕ͂Ƃ���(�؊�)�B�S�ς̒ʖ�ŗ��Ɖ�b���s�����B
ⅺ�j�w�����x�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�w�����x�ɂ��ƁA�m�d�[�i��������j�����ʔN�� (520�N–527�N�j�ɕ}�K�Ƃ�����������ւ���Ă����Ƃ����B�}�K���͓��{�̕ʏ̂Ƃ��ėp������Ƃ��ẮA1094�N�̎j���w�}�K���L�x�̃^�C�g���̗p�Ⴊ�����邪�A����ȑO�ɂ���������A�ŌÂ̗p��͒�ό��N�i859�j�̗Ⴊ����B���{���킴�킴�}�K�Ƃ����ʖ��ł�Ԃ̂́A�O���W�Ȃ����ΊO�I�ɒ������ӎ����������╧���W�Ŏg���邱�Ƃ����������B�d�[�́A�}�K�̏��ݒn�ɂ��ẮA�`���̓��k7000�]���i3000km�]�A����̗� �� 434m�A�ȉ����Z�ɂ͂��̒l���g���j�ɕ��g�����A���̓�5000�]���i2200km�]�j�ɑ势��������A�势���̓�2���]���i8700km�]�j�ɕ}�K������B���{�̕ʏ̂Ƃ��ėp������Ƃ��ẮA1094�N�̎j���w�}�K���L�x�̃^�C�g���̗p�Ⴊ�����邪�A����ȑO�ɂ���������A�ŌÂ̗p��͒�ό��N�i859�j�̗Ⴊ����B���{���킴�킴�}�K�Ƃ����ʖ��ł�Ԃ̂́A�O���W�Ȃ����ΊO�I�ɒ������ӎ����������╧���W�Ŏg���邱�Ƃ����������B
�������A�`���E���g���E�势���܂łɂ��Ă͒n�̕��Ŏ����Ƃ��ď�����Ă��邪�A�}�K�ɂ��Ă͂��̈ʒu���܂߁A�d�[�̏،��Ƃ����`�ŏ�����Ă���B�܂��A�n�̕��̑势���ƌd�[�̌����势�����������̂����͂����肵�Ȃ��B���Ă͕����͂Ȃ��������A�喾2�N�i458�N�j�A罽�o���i�K���_�[���E�J�V�~�[���ߕӁj����5�l�̑m�����ĕ��T�ƕ����������炵�o�Ƃ����߂��̂ŁA�����͕ω������B
ⅻ�j�w���x���x�i����j�́A���̎j�w�Ƃł���L�v����636�N�ɕҎ[�����j���ł���A��\�l�j�̂����̈�ł���B������k������i439�N - 589�N�j�̓쒩�Ō�̉����ł���̒f��j�ł���B�c��E���𒆐S�ɋL�����{�I6���ƁA���Ɏd����Ɛb����ӈٖ����̃G�s�\�[�h���L���ꂽ��`30������̍\���ƂȂ��Ă���A�\��u�������Ȃ��B
11���I����A�k�v�̎j�ُC��ł������\�݂�̎�ɂ���Ċ��s���ꂽ�B
�I�B�j�w�k�j�x�yⅻ.1�w�k�j�x�`���`�z�w�k�j�x�i�ق����j�́A�����̖k���ɂ��ď����ꂽ���j���B����t�ɂ��Ҏ[���J�n����A���̎q�̗������ɂ���Ċ������ꂽ�B��\�l�j�̈�B�S100���ŁA�{�I12���A��`88���̍\���ƂȂ��Ă���B�@��k������i439�N - 589�N�j�̖k���ɂ����鉤���A�k鰁E��鰁E��鰁E�k�āE�k���E�@�̗��j���L���Ă���B�ٗ߂��t���̑���������ď����ɏd����u���A�L�q�̑��ʂ͒f��j�ł���w鰏��x�E�w�k�ď��x�E�w�����x�E�w�@���x�����킹�����ʂ̔����قǂł��邪�A�f��j��4���Ɍ����Ȃ��L�q�����Ȃ��Ȃ��B���Ɂw鰏��x�̋L���Ȃ�������鰂̐l���ɂ��Ă̑��╔�����傫���B
�I�C�j�w��j�x�A�����̓쒩�ɂ��ď����ꂽ���j���B����t�ɂ��Ҏ[���J�n����A���̎q�̗������ɂ���Ċ������ꂽ�B��\�l�j�̈�B�S80���ŁA�{�I10���E��`70���̍\���ƂȂ��Ă���B��k������i439�N - 589�N�j�̓쒩�ɂ����鍑�ƁA�v�E�āE���E�̗��j���L���Ă���B�ٗ߂��t���̑���������ď����ɏd����u���A�L�q�̑��ʂ͒f��j�ł���w�v���x�E�w��ď��x�E�w�����x�E�w���x�����킹�����ʂ̔����قǂł��邪�A�f��j��4���Ɍ����Ȃ��L�q�����Ȃ��Ȃ��B�Ƃ��ɉ����`�̑���Ȃǂɂ���͌����ł���B
�y�I�C-�w��j�x�`���`�z��j�`���`�ł́A�u�`���A���̐�̏o���鏊����я��݂́A�k�j�Ɏ��ڂ����B�v�Ɏn�܂�A�u�`���̕����v�A�u�`�̌܉��v�A�u�ˎE�������E�����v�A�u���g���v�A�u�势���v�A�u�}�K���v�ɂ��ċL�q����Ă���B
�w�`���A���̐�c�̏o���ꏊ�⏊�݂ɂ��Ă͖k�j���ڂ����B�����̊��ɂ͈Ɏx�n������A����\�n�l�x�Ƃ����A���̎���z��鞮�Ƃ����B�l�X�͐���A�I���̎���܂��A�{�\���Č��D����a���B�G�A�j�A�k�A���A�h������B��賁A�^��A�ʂ��Y�o����B���̔@���b������A���͎R�l�A�܂��A���̏b�i�R�l�j��ۂݍ��ޑ�ւ�����B���̎֔�͌����A�@����Ȃ��B��ւ̏㕔�ɍE������A�J����������肵�āA���ɂ͌�������A���̍E�̒����˂�Ύւ͎��ʁB���Y�͂ق�儋�����R�Ɠ����B���y�C��͉��g�A�����͈����ł͂Ȃ��B�j���͊F�A���ɉ������Ȃ����A�x�M�Ȏ҂͋тɗl�X�ȍʂ��D���t���ĖX�q�Ƃ���A�����̌ӌ����Ɏ��Ă���B���H�ɂ͌�V��p����B�����̎��҂ɂ͊��͂��邪�͂Ȃ��A�y���Ē˂����B�l�X�̐����͊F������n�ށB�K���͐��i���j��m�炸�A�����������ŁA���邢�͔��`��\�A���邢�͕S�ɓ͂��B�����̕����͏��������j�͏��Ȃ��̂ŁA���M�Ȏ҂͎l�`�ܐl�̍ȁA�G�����҂ł���`�O�l�̍Ȃ�����B�w�l�͎��i�������A�ޓ��͂Ȃ��A���ׂ͏��Ȃ��B�����@��Ƃ��A�y���҂͂��̍Ȏq��v�����A�d���҂͂��̏@����ł���B�W�̈���̎��i396�|418�N�j�A�`���]������A���g���ȂĒ��v�����B�@�v�̕���̉i����N�i421�N�j�ɁA�قɞH���u�`�̎]�A�����̒������X�����R�����A�����������ׂ��v�B�@����̌��Ó�N�i425�N�j�A�]���܂��i�n���B�����킵�A��\���ĕ��������サ���B�x
�y�I�D�w�@���x�z�@�{�I5���E�u30���E��`50������Ȃ�B���Ɂu�o�Ўu�v���������B����鰒��ƒ��������炪���@�̒���Ē�����s�����B�Ҏ[�ɂ͊�t�Â�E�n�B�炪�Q�������B636�N�i���10�N�j�ɂ�鰒��ɂ���Ė{�I5���E��`50�����������A��3�㍂�@�ɑ�ւ�肵�����656�N�i���c���N�j�ɁA���������ɂ���Ďu30���������A�ғ����ꂽ�B
�y�I�D.1�w�@���x���ΙB�z�w�@���x�́u���Γ`�v�́A��81����`46�ɂ�����B���̏��̒��ł́A������俀���i�`�����}�g�����j�ƁA���̉������v�k�ǂ⒩�N�����ɂ����������E�V���E�S�ςƗ����ɂ��ċL�q����Ă���B�L�q�̏��Ԃ͍����E�S�ρE�V���E�����E�����E�`���ł���B
俀�i�`�j�Ɋւ���L�q�ł́A�r�֎h���s���Ă����Ƃ��������Ɋւ�����́A�܂��������q�����@�m���@�֗��w���������ƂȂǂ����y����Ă���B
�y�I�D.2�w�@���x�^�C���`�z�u�@���v�ł́A���̏��Ɍ�����u�`���v�̂��Ƃ��u�^�C���v(�^�C���ɂ�ׂ�{��)�Ə����Ă���B����́u�ぁ�`�v�A�u��`���i���^�C�v�Ƃ������Ƃł���B
�����Ɂu���o���鏈�̓V�q�A�]�X�v�́u�Γ��O���v�̋L��������̂ɁA�u���{���I�v�̐������q�̋L���ɂ́u���V�c�A�h�݂Đ��c��ɔ����v�Ƃ���B����͗����̋L��������łȂ����Ƃ̉����̏؋��ł���B�܂����̏��́A���̋L�q���炵�āA�㊿�̌�����̋���A�ږ�āA�`�̌܉��A�����āu���o���鏈�̓V�q�v���A�S�ē���̍��̗��j�ł��邱�Ƃ��ؖ�����j���ł�����B�܂�P�ł���B�̂��Ƃł���ΑS�ċ�B�Ƃ������ƂȂ̂�...
�ȉ��A���̎j���ɑ�����߂̎d�����ڍׂɋL�����L�ڂ����������A�����ł���A�u�����̓`�d�v�ɂ͊W�Ȃ��̂ŁA�������܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�y�I�E �������z�u���{�v�̖��̂��ŏ��ɋL�ڂ����j��
�������ɂ͓��{�ɂ��āw�`���x�Ɓw���{���x�̏�������B�u���{�v�̖��̂Ɋւ��Ď��̋L�q������B�����ܑ�\������̌�W�o��̎��ɗ�昫�E�������E�Ɉ܁E������ɂ���ĕҎ[���ꂽ���j���B��\�l�j�̈�B���̐����i618�N�j����ŖS�܂Łi907�N�j�ɂ��ď�����Ă���B�����̌Ăі��͒P�Ɂw�����x���������A�w�V�����x���Ҏ[����Ă���́w�������x�ƌĂ��悤�ɂȂ����B
�����Ƒt���945�N�i�J�^2�N�j6�������A���̗��N�ɂ͌�W���łтĂ��܂����߁A�Ҏ[�ӔC�҂��r���Ō�シ��Ȃ�1�l�̐l����2�̓`�𗧂ĂĂ��܂�����A�����ɏ��ʂ���A�ӓ��͋L�q�������ȂǕҏC�ɑ����̖�肪�������肵���B
���̂��߂Ɍ㐢�̕]���͈����A�k�v����Ɂw�V�����x���ĕҎ[����邱�ƂɂȂ����B�������A�t�ɐ��̎��������̂܂����ʂ����肵�Ă��邽�߁A�����I���l�́w�V�����x���������ƌ�����B
�w�������x���Γ`�̒��ɂ́A���{�ɂ��āu�`���`�v�Ɓu���{���`�v��2���������Ă���A�u��199�� ��B��149�� ���v�ɂ́u���{���� �`���V�ʎ�� �ȑ����ݓ�� �̈ȓ��{ਖ� ���H �`�����������s�� ��ਓ��{ ���] ���{�p���� ���`���V�n[4]�v�Ƃ���A�`������������{�ɉ��߂����A���Ƃ��Ə����ł��������{���`���̒n�������ƋL�q����Ă���B�����āA�v�㏉���́w�����䗗�x�ɂ����̂܂ܓ�̍��ł���|�������p����Ă���B����ɂ��ẮA�Ҏ[�ߒ��̉e���ł���ƍl����̂����{�ɂ�����ʐ��ł���B�٘_�����݂��Ă��āA�Ⴆ�A�X���͂́u���{�v�̍���������̍ŏ��̌����g�ł�����702�N�̔h���̍ۂɂ͍����ύX�̗��R�ɂ��ē��{���ł��s���ɂȂ��Ă���A�����g�������ɗ��R��������邱�Ƃ��o���Ȃ������\�����w�E����B������́A�����P�Ȃ�Ҏ[�ߒ��̃~�X�ł͂Ȃ��u�`���`�v�Ɓu���{���`�v�̊Ԃ̘`���i���{�j�֘A�L���̒�����Ԃɂ́A�����]�̐킢�y�ѐp�\�̗����܂܂�Ă���A�����̒������ɂ́A�p�\�̗��������āu�`���i�V�q�����j�v���|����āu���{���i�V�������j�v�����������Ƃ������������݂��Ă���A���_���o����Ȃ��܂܂ɋL�q���ꂽ�\��������Ǝw�E���Ă���B
�@�@�@�@�@
�y�I�F�w�V�����x�z670�N�Ɂu�`�v�����炽�߂āu���{�v�ƍ������Ƃ̋L�q������܂�
�w�V�����x�����Z�A���Γ��{�`�Ɂw�������N�A���g�ꕽ����A���c�K�ĉ��A���`���A�X�����{�x�Ƃ���A�������N���Ȃ킿670�N�Ɂu�`�v�����炽�߂āu���{�v�ƍ������Ƃ̋L�q������w�������x�ł͘`�Ɠ��{������������Ԃŏ�����Ă��邪�A�w�V�����x�ł́u���{�`�v�Ƃ��Ă܂Ƃ߂��Ă���B
�@�̊J�c���ɓV�c�Ƃ̖ڑ����v��ǂ����߂Ē����ƒʂ����Ə�����Ă���B�����āA���{�̉��̐��͈������ł��邱�ƁA�}����ɂ����_������a�����V�c�ƂȂ������ƂȂǂ��L�ڂ���Ă���B�o�T�͎�����Ă��Ȃ����A�v�j���{�`�̋L������A���厛�̑m�����R���v�̑��@�Ɍ��サ���w���N��I�x���Q�Ƃ����ƍl�����Ă���B�ȏ�̂Ƃ���V�䒆�傩��彥�q�܂ł�32���A�V�c�͐_���V�c�ȉ��c�ɓV�c�܂ŗ���Ă���B�܂����̌�ɂ͌��F�V�c�܂ł��ڏq����Ă���B
�������A�V�䒆�傩��彥�q�܂ł̐����͑v�j���{�`�ł́u��\�O���v�ł���A�S�Ă̖��O������Đ��������Ă��邽�߁A�u�O�\�v�͓�ƎO�����Ⴆ���\���������B�w�Î��L�x��w���{���I�x�ƈقȂ�L���Œ��ڂ����B�܂������g�ɉ�������k�퐨���C���̖���������B�Ō�Ɂu�� �g�� ����O�����v�ɂ��ĐG����i����͖��炩�łȂ��j�A�����͉��v���A���l�A��q���̂��ƂƂ�������B�Ȃ��A������ǂt�r���C�E�n���́A�u���{�ɂ͋����L�x�ɎY�o����Ƃ���v�Ə�����Ă������Ƃ�����{�ɋ����������A�e�������ڂ��Ƃ������A�����̎����ł���k�����@�ɂ����Ȃ��f��ꂽ���Ƃ��t�r���C�̋t�ɂӂ�āA�����ɂȂ������Ƃ����B�X�Ɏ��̂悤�ȋL�q������Ƃ̂��ƁB�u�Â̘`�z���Ȃ�B�V���̓���ɍ݂�A��C�̒��ŕ�炷�B��X�����ƒʌ�����B���̉��̐��͈������B
���ɂ͏\��݂��Ă���B�K���͕���������A�Ŗ@���h���B��韂Ŋ��Ƒт͂Ȃ��B�@�����邪����Ɉߊ��������B���A���\���ȂĊ�������B�ߕ��̍����͑�ϐV���ɗގ����Ă���B���ɋ����̉Ԃ�т�B���������B���E�Ɋe�����B������ȂċM�G�ⓙ���𖾂炩�ɂ���B�v
�����̑�\�I�j���i��\�l�j�j�Ƃ��̓��e�iWikipedia���j�i�n�J�w�j�L�x�njŁw�����x䗞@�w
�㊿���x
�[����w
�W���x
����w
�v���x
���w
�O���u�x
�J�q���w
���x
�L�v���w
�����x
�L�v���w
���x
鰎��w
鰏��x
���S��w
�k��x
�ߌϓ�棻���w
�����x
鰒��E�����������w
�@���x
�������w
��j�x
�������w
�k�j�x
��昫���w
�������x
����ʓ��w
���j�x
���z���E�v�V�w
�V�����x
�L�������w
���ܑ�j�x
���z���w
�V�ܑ�j�x
�E�E���w
�v�j�x
�E�E���w
�Ɏj�x
�E�E���w
���j�x
�v�Q���w
���j�x
��\�l�j�͐���
�������ɂ���Ē�߂�ꂽ�B
���ؖ������Ɏ����āA���j�����߂��w
�V���j�x���Ҏ[����A���{�ɂ���Đ��j�ɉ������ē�\�j�ƂȂ����B�������A�w�V���j�x�̂����ɁA�������������̕Ҏ[�ɂ��w���j�e�x�𐔂��āu��\�j�v�Ƃ���ꍇ������A��肵�Ȃ��B�w�V���j�x�w���j�e�x���Ƃ��Ɋ܂߂��u
��\�Z�j�v�Ƃ����Ăѕ�������Ă���B
�܂��A����E�����1961�N�ɑ�p�������{�̎�ɂ���āw���j�e�x���������Đ��j�Ƃ��Ắw���j�x���Ҏ[���ꂽ���A�k���̒��ؐl�����a�����{�́A���������������}�̎j�ςɂ���āw���j�e�x�������������̂ł���Ƃ��Ă��̑��݉��l��F�߂Ă��Ȃ��B���ؐl�����a���͍��Ɛ��j�Ҏ[�ψ���𗧂��グ�A�Ǝ��́w���j�x��2002�N���Ҏ[���B������2013�N�̊�����\�肵�Ă������A���e�ɖ��S�������邽�߁A���x���摗�肳��Ă���B2019�N���݁A���N���̊�����������ł���B
��\���i�ŏI��j�@��